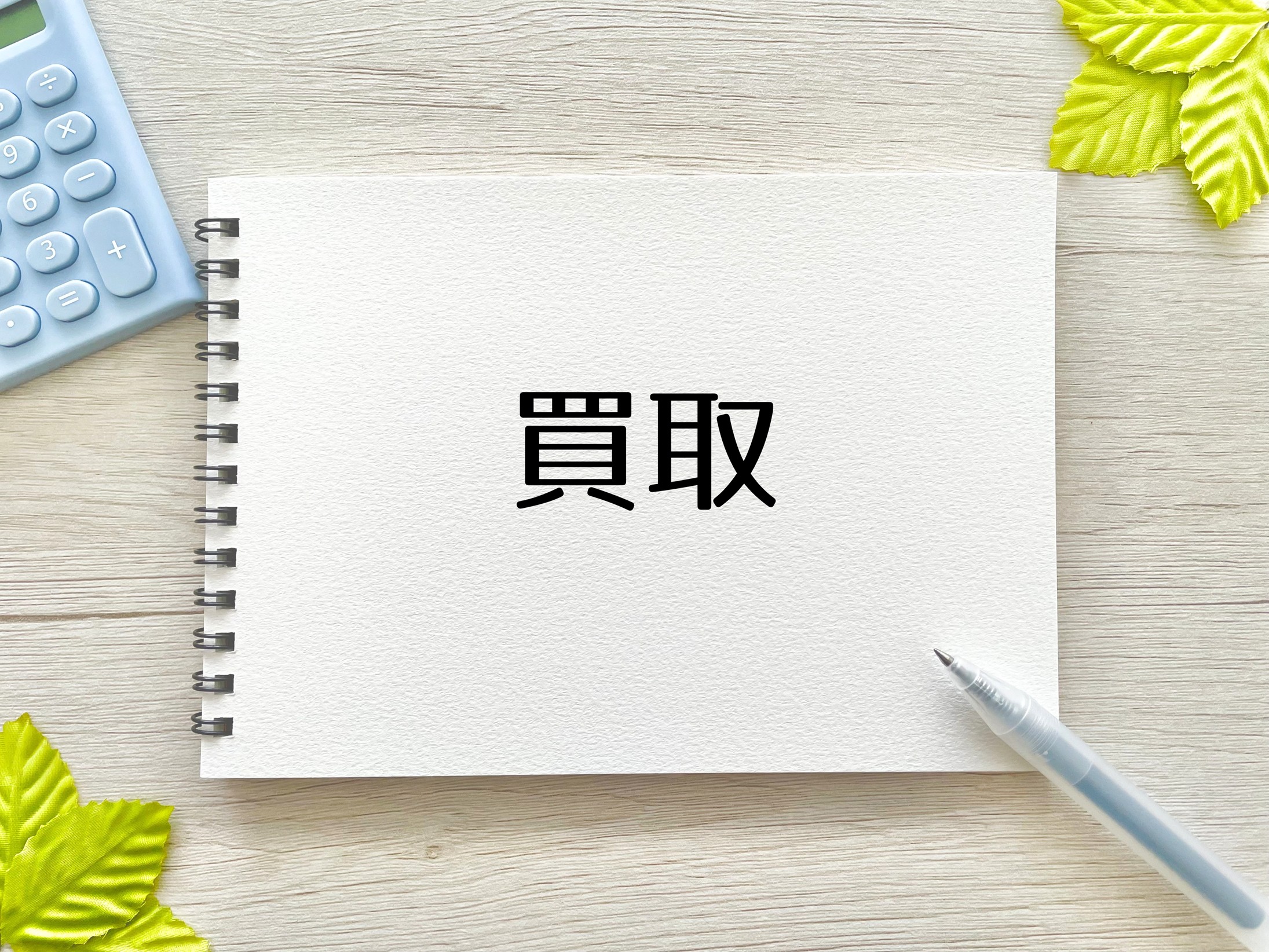電話でのお問い合わせは03-5695-2341
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18-20
「共有持分」とは?共有不動産の売却方法について

「共有持分」とは?共有不動産の売却方法や税金について解説します|東京都心に特化した高額買取実現。無料査定は24時間メールで受付中です。東京28区の不動産売却なら【蔵正地所株式会社】
目次
1.共有持分とは
まずは、共有持分を理解するための用語についてそれぞれ確認しておきましょう。
・共有者
1つの不動産を複数人で所有している状態を「共有している」と表現します。共有不動産とは、所有している人が複数いる不動産であることを示しており、所有するそれぞれの人は共有者と呼ばれます。夫婦で1つの不動産を所有している場合、共有者は夫と妻ということになります。
・共有名義
共有名義とは、1つの不動産を所有している人が複数名いる状態を指しています。名義とは、書類上に所有者であることを示す表現方法の一つです。不動産を夫と妻で購入した場合、物理的に存在する不動産は1つしかありませんが、書類上の不動産所有者は夫と妻の2名いることになります。不動産は夫と妻の共有名義である、という表現をします。ちなみに、不動産を所有できる名義人の人数には制限がありません。遺産相続などで不動産の共有人数が10人以上になるケースも実際に発生しています。
・共有持分
共有持分とは、不動産に対して各共有者が所有している概念上の権利割合のことです。複数人で一つの不動産を所有している共有名義の不動産の場合、不動産は1つしかありませんので、物理的に分割してそれぞれの分だけ使うというのは現実的に不可能です。そのため書類上で共有者が所有する割合を数値で記録しておくことで、税金の計算や不動産の扱いに対して意思決定を検討する際の票数計算がしやすくなります。
・持分割合
不動産を共同で所有している各共有者に対して、持分として割り当てられた概念上の割合のことです。2分の1など分数で記載します。持分割合の具体的な数値については、固定資産税通知書より確認することができます。固定資産税通知書とは、毎年市町村から郵送で送られてくる不動産にかかる税金についての納税をお知らせする書類です。こちらの書類は不動産所有者の代表者に対してのみ送られますので、代表者以外の方が自分の持分を確認したい場合は、各自治体で発行される固定資産評価証明書や不動産の登記事項証明書を取得します。
2.共有持分のメリットとデメリット
不動産を共有で所有する際のメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
・メリット
住宅ローン控除を共有者の分だけ受けられる
1つ目のメリットとして、住宅ローン控除を共有者の分だけ受けられる点があります。夫婦二人で共有している場合、夫婦それぞれに住宅ローン控除が適用されるため、二重で控除が受けられることになります。住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高に対して1%(最大50万円)の税額控除を10年間に渡って受けられる制度です。ただし、2022年の法改正で期間が13年まで伸びたものの、控除率が0.7%(最大35万円)に引き下げられており、今後も変更の可能性はあるため利用する際に改めて確認する必要はあります。
不動産の売却時にも控除を二重で受けられる
2つ目のメリットは、不動産の売却時にも控除を二重で受けられる点です。居住用の共有不動産を売却する場合、「居住用財産特別控除の特例」が適用されれば、譲渡利益に対して最大3,000万円までの控除を受けることができます。夫婦で共有する不動産を売却した場合、両者に特例が適用されますので、不動産の譲渡利益に対して6,000万円までの控除を受けられることになります。ただし、居住用の不動産の売却で6,000万円の利益が出ること自体稀なケースと思われますので、特別控除を受けられることを理由に不動産を共有名義にすることはあまりおすすめできません。
相続税の負担を抑えられる
3つ目のメリットは、相続税の負担を抑えられる点です。夫婦で住宅を購入している場合、万一夫が亡くなり、妻が相続するとなれば相続税が課税されます。この時不動産の名義が夫だけであれば不動産評価額の全体に対して相続税が発生しますが、夫婦の共有名義にしておけば夫の持分にだけ相続税が発生しますので、支払う税額をおさえることができます。
・デメリット
共有者の承諾がないと売却できない
一方デメリットとしては、共有者の承諾を得られなければ不動産を自由に売却できない点が挙げられます。不動産が共有名義になっている場合、売却をする際は共有者全員の同意が必要になります。売りたい時にすぐに行動にうつせないことはデメリットになるでしょう。ただし、売りたくない場合は共有者に勝手に売らせないという点でメリットになるケースもあります。夫婦の離婚などで今後もしばらく自宅での居住を続けたい場合、離婚相手は共有者の同意なしに勝手に自宅を売却してしまうことはできません。一時的な措置になる可能性はありますが、一方的に追い出されてしまう心配はありません。
離婚すると売却せざるを得なくなる
離婚してすぐ勝手に売却されることはありませんが、ゆくゆくは手放さないといけなくなる可能性はあります。理由としては、住宅購入時の支払い負担は自分の持分だけでしたが、離婚して住宅の全ての持分を譲り受けるとなると、支払いの負担が倍増するからです。購入時の持分が2分の1なら今後の支払額が2倍に、購入時の持分が3分の1なら支払額は3倍に膨れ上がります。相手に勝手に売られることはないにしても、支払い能力がなければ売却せざるを得なくなってしまいます。
贈与の対象になる
支払いの負担が増えるケースは離婚だけではありません。夫婦どちらかが仕事を辞めるなど、収入が止まる場合も同じことが言えます。夫婦の一方の収入が止まるケースでは、住宅ローンが残っている場合には支払いの負担が増えることになります。また、その持分を贈与する場合は贈与税がかかることになりますが、110万円の基礎控除がある他、婚姻関係が20年以上続いていれば2,000万円まで配偶者控除を受けることができるため、制度を利用すれば贈与税の負担はおさえることができます。
相続の対象になる
不動産の共有者が亡くなってしまった場合、亡くなった共有者の持分が他の相続人である共有者に相続された場合には相続税の課税対象になります。また共有者以外に他に相続人がいる場合には共有持分がより細分化・複雑化してしまうため、不動産の処分が難しくなる恐れがあります。
3.共有名義で資産を所有する際の注意点
- 持分は別れているが全部を使用できる
- 共有物を処分する際は全員の承諾が必要
- 共有物の管理をする際は過半数の持分が必要
- 保存行為の場合は他の共有者の承諾は不要
- 各自の持分の処理は自由
4.共有持分を所有したままできること
共有持分だと何かと不便に感じることがありますが、共有持分のままでもできることはあります。ケース別にできることをご紹介します。
・ひとりでできること
共有物の使用
所有する割合は自分の持分として分割されていても、不動産の使用については物理的な範囲の制限などはなく自由に使うことができます。夫婦で不動産を所有する場合、持分は2分の1ずつや3分の1と3分の2などに設定しますが、実際に使用する時に物理的な制限がないのと同様です。ただし、複数人で所有している場合、皆が同居でもしていない限りはそれぞれの都合に合わせて使用することになります。お互いの使用日が重ならないよう事前の話し合いなどが必要となるでしょう。
修繕
共有する不動産を代表者が管理する場合、基本的には所有者全員の承諾を得ながら運営を進めていきますが、水漏れや雨漏り、電気系統設備の故障の際は、他の共有者の承諾を得ることなく修繕を実施することができます。理由としては、水漏れや故障は修理の緊急性が高い事項であり、かつ不動産の現況を大きく変容させるような大がかりな工事でもないからです。ただし、緊急を要する修繕という名目で好き勝手されるのは困りますから、事後報告だとしても、修繕内容を報告させるなど共有者同士が納得できる体制を整えておくと良いでしょう。
侵害行為に対する対処
共有持分の所有者として行使できる権利を侵害するような行為への対処については、他の所有者の同意を得ずに、単独で実行することができます。侵害行為というのは、不法な占拠や不正な登記手続きなどです。不法な占拠としては第三者や浮浪者の無許可の住み着きなどがあり、直接説得や裁判所への申立てなどの対処が可能です。また、不正な登記としては共有持分を勝手に単独持分への変更などがあり、発見した場合には他の所有者の承諾を得ることなく抹消請求をすることができます。
共有持分の売却
他の所有者の承諾を得ずに実行できる行為として、自身が所有する共有持分の売却があります。全体としての不動産を売却するには所有者全員の承諾が必要になりますが、自分の持分のみであれば売却など自由に処分して問題ありません。ただし、共有持分というのは第三者と不動産を共有することであり、所有しても取り扱いの自由が制限されていることから、相場よりも低い評価額で取引されることがほとんどです。少しでも高く売りたい場合は専門の不動産会社に相談してみることをおすすめします。
・共有者の過半数を超える承諾を得られさえすればできること
共有者全員の承諾がなくても過半数を超える承諾を得られさえすればできる行為も存在します。ただし、過半数を超える数の承諾が必要ですから、共有者が夫婦の場合どちらか一方だけでは過半数を超えることができませんので、両者の承諾が必要になります。
改良
共有持分の過半数を超える承諾を得られた際にできる行為の一つに、リフォームなどの改良行為があります。修繕などは単独でおこなうことができますが、リフォームとなると現況を変更する行為になるため、半数を超える同意が必要になるのです。ただし、資産価値の向上を目的とした行為と認められるため、所有者全員の承諾がなくとも実施することは可能とされています。
短期間の賃貸
短期間の賃貸行為についても、所有者の過半数の同意を得られれば認められています。短期間とは、土地の賃貸なら5年以内、建物の賃貸なら3年以内と定められています。短期間の賃貸が認められている理由は、共有物の性質を変更せずに収益をあげる管理行為にあたると考えられるからです。単独の場合は保存と使用行為が、過半数を超える場合は管理行為が認められていると民法で定められています。
・所有者全員の同意が得られるとできること
最後に所有者全員の同意が得られるとできることを解説します。つまりは全員の同意が得られなければ実施してはいけない行為でもあるので注意してください。
資産全体の売却
所有者全員の同意が必要なケースは資産の「変更」に当たる行為や共有者の権利に大きな影響を与える行為です。その一つに該当するのが資産全体の売却です。資産を売却すると共有者としての権利を手放すことになりますから、影響が大きいと考えるのが妥当です。ですので、資産の売却を検討する際は所有者全員の承諾が必要になります。
抵当権の設定
共有不動産を抵当権に設定する際も、所有者全員の承諾が必要です。抵当権とは借金の担保にする行為ですから、抵当権が実行されれば所有者は不動産を手放さなければなりません。抵当権の設定は所有者としての権利に大きな影響を与えかねない行為に該当します。ただし、資産全体の売却にも言えることですが、自分の持分についての売却や抵当権の設定の場合は他の所有者の同意を得る必要はありません。
長期間の賃貸
短期間の賃貸で規定されている年数以上の賃貸をおこなう際は、所有者全員の同意を得る必要があります。理由としては、長期間の利用は所有者の権利に大きな影響を与えるからです。また、土地に新しく建物を建てるなどのケースも全員の同意が必要になりますので、何か所有する不動産に関する活動をする際はどのような手順で進めれば良いか確認しながらおこないましょう。
5.共有持分の放棄について

共有不動産を管理するのに逐一共有者の同意を確認するのを面倒に感じる人もいるでしょう。自分の持分だけであれば、所有を放棄することが可能です。
・所有権移転登記で共有持分を放棄
放棄する方法としては、登記上の所有権を移転する手続きがあります。登記の移転には他の所有者の確認が必要になるため、協力してもらえるよう事前に相談すると良いでしょう。共有持分を放棄することで、煩わしい管理の手間がなくなり、固定資産税などの税金を納める必要がなくなります。
・登記取引請求訴訟で共有持分を放棄
移転登記が他の所有者に認められない場合、訴訟をすることで手続きを進めることができます。訴訟が認められれば、他の所有者の同意なしに登記の移転手続きができるようになります。ただし、訴訟内容が認められるまで数か月はかかりますから、訴訟期間の所有は受け入れる必要があります。
6.共有持分の売却について
共有している不動産の売却について解説します。
・自身の持分は売却可能
自身の持分であれば、他の所有者の同意なしに売却できます。ただし、購入者は他人と不動産を共有しなければならず扱いも難しいため、相場の半額程度で取引されるケースもあります。
・不動産そのものを売却したいケース
不動産そのものを売却したいは場合、所有者全員の承諾を得る必要があります。仮に売却したい所有者が複数人いる場合には、所有する土地を売却したい所有者と、そのまま共有で保有したい所有者とで話し合い、その持分に応じて土地を二区画に分筆(道路状況等により分筆できない場合もあります)し、売却側と保有側にそれぞれ名義を移転し、売却したい共有者の土地だけを売却することも可能になります。
・不動産を貸したいケース
不動産を貸したい場合は、賃貸する期間によって必要な同意の数が異なります。建物の場合3年以内の賃貸であれば所有者の半数の同意が、3年を超える場合は全員の同意が必要です。土地の賃貸の場合は5年が求められる同意数の分かれ目になります。
7.共有持分を売却する方法
共有持分を売却する具体的な手順や方法を解説します。
・他の共有者に相談
売却を検討する際は、まずは他の所有者へ相談するようにしましょう。自分の持分であれば同意なしに売却できますが、無用なトラブルは避けた方が良いからです。一言でも声がけをするなどしてコミュニケーションを取っておくと良いでしょう。
・専門の業者に相談する
一般の不動産会社では共有持分についてのノウハウが少ない場合がありますので、共有持分について実績のある不動産会社に相談するようにしましょう。売却後にトラブルにならないよう、丁寧で誠実な姿勢で取り組んでくれる業者を選ぶことをおすすめします。
・所有者全員の同意を得て不動産全体を売却する
理想的な形としては、所有者全員の同意を得て不動産全体を売却することです。売却後のトラブルを避けられるだけでなく、相場価格での売却が可能だからです。売却益は所有者同士で分け合い、スムーズに手続きを完了できます。
・他の共有者に購入してもらう
新しい買い手が赤の他人ですと不信感に繋がりますから、他の共有者に購入してもらうのも一つの方法です。売却価格で揉めないよう、不動産鑑定士などに適切に価格を評価してもらうと良いでしょう。
・土地を分筆して単独名義に切り替えてから売却する
多少の荒技にはなりますが、土地を分筆して単独名義に切り替えてから売却する方法もあります。分筆しただけでは分割した土地をそれぞれ共有しているだけになりますが、単独名義に切り替えることで、独断で売却できるようになります。ただし、分筆することで他の土地に不利益が出ることもありますので、分筆後を考慮して手続きを進める必要があります。
8.共有持分を売却する際の費用
共有持分の売却時にかかる費用をご紹介します。
・登記費用
共有持分を売却する際は、不動産の所有名義を変更するための登記費用(登録免許税)がかかります。
・譲渡所得税
不動産の売却で利益が発生した場合、所得税と住民税、復興特別所得税からなる譲渡所得税を支払う必要が出てきます。所得税の割合は、保有期間5年以内の短期譲渡の場合は39.63%、5年以上の長期譲渡の場合は20.315%です。
・印紙税
不動産の取引をおこなう際は、売買契約書に貼付する印紙税がかかります。500万円を超え1,000万円以内の取引なら1万円、1,000万円を超え5,000万円以内の取引なら2万円、5,000万円を超え1億円以内の取引なら6万円の印紙税がかかります。
・仲介手数料
不動産会社へ支払う仲介手数料の支払いも発生します。400万円以上の取引であれば、3%+消費税が手数料の割合となっています。
9.共有持分を売却する際に必要な書類
共有持分を売却するのに必要になる書類は以下のとおりです。
不動産についての書類
売却する不動産について、以下の書類が必要になります。
- 権利証(登記識別情報)・・・名義変更に必要な書類で法務局にて取得できます。
- 測量図および境界確認書・・・土地の境界を確認するための書類で法務局にて取得できます。
- 固定資産評価額の証明書・・・不動産の価値の確認や税金を計算するための書類で市町村役場にて取得できます。
個人の書類
個人としては、印鑑証明書など不動産取引に適した書類を用意します。
- 身分証・・・本人確認書類を用意します。
- 住民票・・・登記簿上の住所との相違がある場合に取得します。
- 実印・・・役所に登録をしている印鑑です。
- 印鑑証明書・・・印鑑を役所に登録していることを証明する書類です。
- 委任状・・・第三者に委任する場合に必要になります。
10.共有持分を売買した場合にかかる3つの税金
共有持分を売却する際にかかる費用のところでも触れましたが、共有持分を売却して利益を得た場合、所得税・住民税・復興特別所得税の3つの税金がかかります。また、売却した不動産を所有していた期間によって、税金の割合が変動しますので注意してください。保有期間が5年以内の短期の場合は39.63%、5年以上の長期になる場合は20.315%となりますので、長期で保有することで税負担が半額近くに軽減されます。
11.共有持分の放棄した場合の税金について
放棄された共有持分を受け取った場合の税金についてご紹介します。
・元の所有者が放棄した場合の税金
元の所有者が放棄した分の持分は、均等に分割して現在の所有者に振り分けられます。この場合、贈与税の課税対象になりますので、110万円を超える分については税金が発生します。
・元の所有者が亡くなった場合の税金
元の所有者が亡くなったために放棄された持分については、相続人に相続され、相続税が課せられます。相続人がいない場合には、放棄のケースと同様に現在の所有者に振り分けられますが、遺贈という扱いになるため、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。
まとめ
共有持分について解説しました。自身の共有持分については自由に扱えますが、トラブルを避けたい場合はできるだけ所有者全員の承諾を得ながら手続きを進めていく方が無難です。自分の力では難しいと感じる場合はプロへ相談してみることをおすすめします。この記事が共有持分についての問題解決にお役に立てれば幸いです。
この記事の監修者

小川 竜二 Ryuji Ogawa
蔵正地所株式会社/代表取締役
《資格》宅地建物取引士