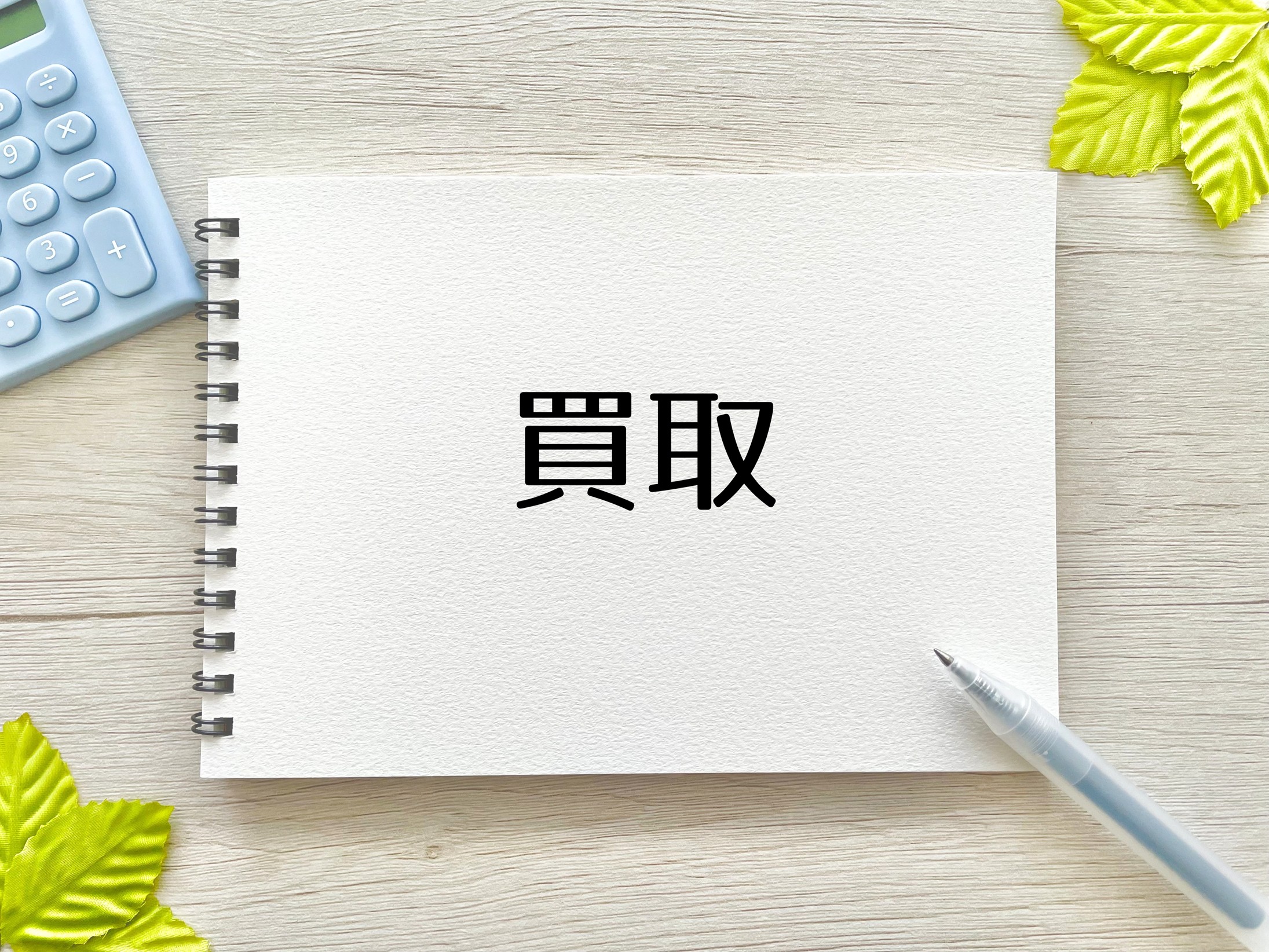電話でのお問い合わせは03-5695-2341
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18-20
共有持分は売却できる?トラブル防止策や相場・発生する税金を解説

共有持分の処分に困り、売却したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
自分の共有持分は、ほかの共有者に同意を得ることなく処分できますが、売却後に想定外のトラブルに発展するおそれがあります。
リスク軽減の観点から、売却活動を進めるまえの準備が重要です。
本記事では、共有持分の売却時に発生しやすいトラブルと回避策をまとめました。
売却相場や発生する税金も解説するため、持分売却の見通しを立てたい方は参考にしてください。
共有持分は同意なしで売却できる?民法上のルールを解説
共有名義の不動産において、自分の「持分のみ」はほかの共有者の同意を得ることなく売却可能です。
共有不動産を、兄弟で所有しているケースを考えてみましょう。
| 項目 | 共有持分割合 | 不動産売却への意見 |
|---|---|---|
| 兄弟A | 3分の1 | 反対 |
| 兄弟B | 3分の1 | 反対 |
| 自分 | 3分の1 | 賛成 |
上記のように、ほかの兄弟が不動産の売却に反対しても、自分の共有持分(3分の1)は自由に処分できます。
ただし、共有持分を「第三者」に売却する場合は注意しましょう。
自分の代わりに、買主が「新たな共有者」として共有関係に入ってくるからです。
事前に兄弟(ほかの共有者)へ売却の旨を知らせておかないと、不動産の権利をめぐって揉める危険性があります。
参考:民法第206条|e-Gov法令検索
共有持分を売却したらどうなるのか
共有持分を売却した際の経済的な影響として、おもに以下の2点があげられます。
- 自己持分を現金化できる
- 贈与とみなされる可能性がある
想定外の税金が発生する可能性があるため注意しましょう。
自己持分を現金化できる
共有持分を売却すれば、売却益が得られるだけでなく、修繕費や固定資産税などの費用負担からも解放されます。
不動産を所有する必要がない場合は、売却を検討してもよいでしょう。
自己持分の売却先・売却方法は、おもに以下の3つです。
- 共有者の間で売買する
- 仲介業者に依頼して買主を探す
- 専門の買取業者に売却する
仲介業者や買取業者に依頼する場合は、買主が「第三者」となります。
他人が「新たな共有者」として共有関係に入るため、当事者間の関係性悪化を招きかねないことに注意しましょう。
ほかの共有者に買取の意思があるかどうか、業者に依頼するまえに確認しておくことが重要です。
贈与とみなされる可能性がある
共有持分を親族間で売買する場合、売却価格に注意を払う必要があります。
相場と乖離した、安すぎる価格で売却すると「贈与」とみなされる可能性があるからです。
贈与とみなされると、買い手(受贈者)に贈与税が課されます。
たとえ売却する相手が子どもや兄弟などの親しい相手であっても、相場にもとづいた価格で売却しましょう。
第三者の専門家が関与すれば、親族間の売買であっても取引の正当性が認められやすくなります。
贈与税の課税を避けたい場合や、トラブルを防止したい場合は、不動産会社に仲介の依頼を検討しましょう。
共有持分の売却で発生しやすいトラブル4選

共有不動産の自分の持分は、単独で売却可能です。
しかし、ほかの共有者に以下のような影響を与えるため、深刻なトラブルに発展する懸念があります。
- 買取業者から連絡が来る
- 共有物分割請求訴訟を起こされる
- 新たな共有者に家賃を請求される
- 離婚時に揉める
どのような事態が起こりうるのか、詳細を見ていきましょう。
買取業者から連絡が来る
買取業者に自分の持分を売却すると、買取業者がほかの共有者に「あなたの持分も売ってください」と連絡することがあります。
買取業者は、買い取った持分を売却することで利益を得ています。
ほかの共有者の持分もすべて買い取って不動産全体の所有権を獲得し、より高値で売り出したいのです。
ほかの共有者は、見知らぬ人から唐突に営業されて初めて、不動産を第三者と共有していることを知ります。
「勝手に売ったのか」「なぜ事前に相談しなかったのか」と共有者の怒りを買い、衝突が起こる事例も少なくありません。
共有物分割請求訴訟を起こされる
共有物分割請求とは、共有者の1人が不動産の共有状態の解消を求めることです。
自分の持分を買取業者に売却した場合、買取業者がほかの共有者に対して「共有物分割請求訴訟」を起こす可能性があります。
共有状態を解消する方法は、裁判の判決によって決まります。
| 判決 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産を分割し、共有者で分ける方法 |
| 代金分割 | ほかの共有者の共有持分を買い取り、単独名義にする方法 |
| 競売分割 | 不動産を競売にかけ、売却代金を分ける方法 |
判決次第では、ほかの共有者も不動産を手放さなければなりません。
不動産に「住み続けたい」と考えている共有者がいると、大きな問題に発展する可能性があるでしょう。
新たな共有者に家賃を請求される
共有名義の不動産に住んでいない人は、居住者に自分の共有持分に応じた家賃を請求できます。
- 20万円の家賃相場の家を、AとBが2分の1ずつ共有している
- Aのみがこの家に住んでいる
上記の場合、BはAに対して持分割合に応じた家賃(10万円)を請求可能です。
親族間で不動産を共有していると、家賃のやり取りをしていないケースも多いでしょう。
しかし、共有持分の売却によって第三者が共有関係に加わると、新たな共有者(買主)から家賃を請求されるおそれがあります。
いきなり家賃を請求された共有者は、まったく想定外の出費になり得ます。
共有持分の売却に同意してもらう義務はないものの、トラブル回避の観点から事前に通知しておくのが賢明です。
離婚時に揉める
夫婦で共有名義の家を所有している場合、離婚する際は「自分の共有持分を売却したい」と考えるでしょう。
しかし、離婚する前に共有持分を売却すると、財産をめぐって後々揉める可能性があります。
家は財産分与の対象で、財産分与の割合は「50%ずつ」となることが原則だからです。
- 家を「夫:80%」「妻:20%」の持分割合で所有している
- 離婚することになり、夫が80%の共有持分を売却した
上記の場合、夫は30%分の代金(50%との差額)を多く獲得していることになります。
共有持分の売却益は、財産分与の対象として最終的に清算するケースもあるため注意しましょう。
共有持分の売却トラブルを防ぐ方法
共有持分の売却では、親族や買主(新たな共有者)とのトラブルがつきものです。
以下のような、未然防止策を講じておきましょう。
- ほかの共有者に売却の意向を伝えておく
- 「買取業者」と「仲介業者」は目的に合わせて選ぶ
- 専門家から助言を得る
- トラブル対応がスムーズな業者を選ぶ
詳細を解説します。
ほかの共有者に売却の意向を伝えておく
第三者に売却した際は、事前に通知していないことがトラブルの火種になり得ます。
法律上の義務はなくても、売却の理由を説明したうえで理解を得ることが重要です。
売却の意向を伝えることで、ほかの共有者が買取を申し出る可能性もあるでしょう。
共有者間で取引できれば、スムーズに共有関係の解消が進むため、双方にとってメリットがあります。
「買取業者」と「仲介業者」は目的に合わせて選ぶ
共有持分を第三者に売却する場合、売却先の選択肢には「買取業者」と「仲介業者」があります。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 買取業者 |
|
| 仲介業者 |
|
どちらの売却先が適しているかは、目的や状況によって異なります。
業者を選ぶ際は、共有持分の取り扱い実績や、会社・担当者の信頼性を確認することが重要です。
専門家から助言を得る
共有持分の売却における共有者間のトラブルは、法的リスクを伴います。
とくに以下のようなケースでは、当事者同士での解決が困難なため、専門家へ事前に相談しておくのがよいでしょう。
- 共有者間で不動産の運用・売却方針がまとまらない場合
- 話し合いの余地がないほど関係性が悪化している場合
- ほかの共有者と音信不通が続いている場合
共有関係が不必要に長引くと、毎年税金がかかり続けることに加え、共有者の死亡により権利関係がさらに複雑化する懸念もあります。
早期に共有関係の解消を図るためには、不動産会社や弁護士、税理士などの専門家に仲介してもらうことも1つの方法です。
トラブル対応がスムーズな業者を選ぶ
共有者間でのトラブルが予見される場合、頼りになるのは弁護士です。
しかし、自力で信頼できる専門家を探すには相応のコストがかかります。
「弁護士対応やトラブル解決をすべて外部に任せたい」という場合は、共有持分専門の業者へ相談しましょう。
共有持分に強みがある不動産会社は、さまざまなリスクを想定して専門家とパートナー関係を結んでいることが多いからです。
業者を選ぶ際は、対応の流れや法律事務所との連携体制などを事前に確認しておくことで、スムーズな解決を実現できます。
共有持分の売却にかかる税金・費用

共有持分の売却では、場合によって少なくない支出が発生します。
一般的に必要になる税金・費用の種類は、以下のとおりです。
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登記費用
- 仲介手数料
負担額の目安を紹介します。
譲渡所得税
共有持分の売却で利益が出た場合、売却益(譲渡所得)に所得税や住民税が課されます。
譲渡所得にかかる税率は、不動産の保有期間によって異なります。
| 項目 | 不動産の保有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 |
|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 |
|
(※)「復興特別所得税」として所得税の2.1%が上乗せられている
一定の要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例を適用可能です。
参考:国税庁|土地や建物を売ったとき
印紙税
契約書や領収書を作成する際にかかる税金です。
共有持分の売却において、買主と交わす売買契約書の作成時に発生します。
印紙税は、売買価格に応じて以下のように異なります。
| 売買価格 | 課税額 |
|---|---|
| 100万円超〜200万円以下 | 200円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 500円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
参考:国税庁|不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
登記費用
共有持分を売却する際には、不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う必要があります。
対象の不動産に抵当権がついている場合、抵当権の抹消登記も必要です。
具体的には、以下のような費用がかかります。
| 項目 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 所有権移転登記にかかる税金 |
|
| 抵当権抹消登記にかかる税金 | 1,000円(不動産1個につき) | |
| 司法書士報酬 | 登記を司法書士へ依頼する場合にかかる費用 |
|
仲介手数料
共有持分の売却時に、不動産会社へ仲介を依頼するとかかる費用です。
仲介手数料は、売却金額によって上限額が定められています。
| 売却価格 | 上限額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売却金額の5%+消費税 |
| 200万円超〜400万円以下 | 過半数の持分で可能 |
| 400万円超 | 売却金額の3%+6万円+消費税 |
たとえば、共有持分を300万円で売却した場合、仲介手数料は最大で「300万円×4%+2万円=14万円+消費税」となります。
参考:国土交通省|不動産取引に関するお知らせ
共有持分の売却相場
共有持分の売却額は、以下の式で算出できます。
ただし、実際の売却相場は「売却先」によって大きく異なります。
以下の2パターンに分けて市場価格の計算方法を見ていきましょう。
- ほかの共有者に売却する際の相場
- 専門の買取業者に売却する際の相場
それぞれ解説します。
ほかの共有者に売却する際の相場
もっともスムーズかつ高値での売却を実現しやすいのは、自分の持分をほかの共有者に買い取ってもらう方法です。
共有者にとっては自分名義の持分が増えるため、不動産を利活用しやすくなるメリットがあります。
実際の売却価格は「共有不動産(全体)の評価額×持分割合」の計算式をもとに、当事者間の話し合いで決定します。
法律上の定めはないため、双方が納得すればどのような条件でも売却可能です。
ほかの共有者が以下の条件を満たしているときは、買取を交渉しやすいでしょう。
- 共有者が不動産を単独で利用している
- 共有者に不動産を買い取る資金力がある
- 共有者との関係が良好、もしくは話し合いの余地がある
共有者に資金力がない場合や、交渉がまとまらない場合は実現できません。
専門の買取業者に売却する際の相場
ほかの共有者が買取に応じない場合は、第三者に売却するしかありません。
買取業者に共有持分を売却する際の相場は、おおむね以下のとおりです。
たとえば、共有持分の市場価格が1,200万円だった場合、買取業者への売却額は400万円〜600万円程度になります。
市場価格よりも大きく値下がりするため「自力で一般の買い手に売るべきでは?」と感じるかもしれません。
しかし、共有持分を見知らぬ個人に購入してもらうのは難しいでしょう。
共有者と無関係の第三者が共有持分を得たところで、以下のようなリスクを負うからです。
- 不動産の一部の権利しか得られず、使い道がない
- ほかの共有者と交渉し、合意を得なければ不動産を活用できない
- 共有者間のトラブルに巻き込まれやすい
こうした不動産を「欲しい」と感じる個人はいないため、共有持分の買取に強みのある専門業者に依頼するのがスムーズかつ確実です。
共有持分の売却でよくある質問

共有持分の売却は、多くの方にとって初めての経験です。
そのため、以下のような疑問が発生しやすくなります。
- 共有持分を購入する買取業者の目的は何ですか?
- 共有持分を売却した際は確定申告が必要ですか?
- 共有持分の売却で3,000万円控除は受けられますか?
- 共有持分は無償で譲渡できますか?
スムーズな売却を実現するため、事前に回答を確認しておきましょう。
共有持分を購入する買取業者の目的は何ですか?
共有持分の買取業者は、不動産を有効活用し、収益性を高めるために活動しています。
具体的な目的は以下のとおりです。
- 共有持分を買い集め、不動産全体の権利を得て市場価値の高い状態で売却する
- 共有持分をほかの共有者に転売する
業者にとっては買取価格と売却価格の差額で利益を得られ、売主にとっては共有関係を早期に解消できるメリットがあります。
共有名義の不動産は自由な利活用が困難で、トラブルに発展するリスクを伴うため、業者が介入して処分する事例が増加しています。
共有持分を売却した際は確定申告が必要ですか?
共有持分を売却した際に、利益(譲渡所得)が発生した場合は確定申告が必要です。 損失が出た際も、以下の控除を利用する場合は申告を検討しましょう。
- 赤字(損失)を翌年以降に繰り越す「繰越控除」
- 赤字(損失)を給与所得などと相殺できる「損益通算」
確定申告の要否を、一覧表にまとめました。
| 条件 | 確定申告の要否 |
|---|---|
|
必要 |
|
必要 |
|
不要 |
確定申告のタイミングは「不動産を譲渡した年の翌年2月16日〜3月15日」です。
期限直前に慌てることのないよう、譲渡所得の計算は早めに行っておきましょう。
参考:国税庁|不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
参考:国税庁|損益通算
共有持分の売却で3,000万円控除は受けられますか?
共有持分の売却では、以下の3,000万円控除を受けられる可能性があります。
| 特例 | 内容 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 空き家特例 | 相続した空き家を売却した際、譲渡所得から3,000万円が控除される |
|
| マイホーム特例 | マイホームを売却した際、譲渡所得から3,000万円が控除される |
|
適用要件の詳細や、税金の計算方法は、以下の記事で解説しています。
内部リンク「相続不動産 売却」
参考:国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
参考:国税庁|共有のマイホームを売ったとき
参考:国税庁|マイホームを売ったときの特例
共有持分は無償で譲渡できますか?
共有持分を欲しがる第三者(個人)を見つけるのは困難ですが、ほかの共有者であれば無償譲渡に応じる可能性があります。
たとえば、弟と2分の1ずつの割合で不動産を所有している場合、弟に自分の持分を譲渡すれば、不動産は弟の単独名義になります。
弟は不動産を自由に利活用できるため、譲渡される側にもメリットがあるでしょう。
ただし、譲渡を受けた共有者には「贈与税」が課されます。
税金がかかることを事前に伝えておかないと、トラブルに発展するおそれがあるため注意しましょう。
まとめ:共有持分の売却時は信頼できる業者を選ぼう
不動産の共有関係は、物件の利活用を促進するためにも早期に解消するのが賢明です。
共有持分の取り扱いには法的・感情的な配慮が必要なため、売却を検討する際は共有トラブルに慣れた買取業者を利用しましょう。
共有持分の処分に悩んでいる方は、蔵正地所をご利用ください。
創業30年にわたる共有持分の買取実績をもとに、お客様にとって最適な提案をいたします。
共有者とのトラブルには法律事務所と連携し、責任を持って対応する体制を整えています。
相続や離婚、その他の事情で共有持分にお困りの方は、蔵正地所にお問い合わせください。
関連記事:相続不動産を売却するには?流れや3,000万円控除・注意点を解説
関連記事:不動産共有名義を買取業者に売却するメリット|事例や相場・税金を解説
関連記事:共有不動産を現金化する方法とは?高値で売却するコツや手順を解説
この記事の監修者

小川 竜二 Ryuji Ogawa
蔵正地所株式会社/代表取締役
《資格》宅地建物取引士