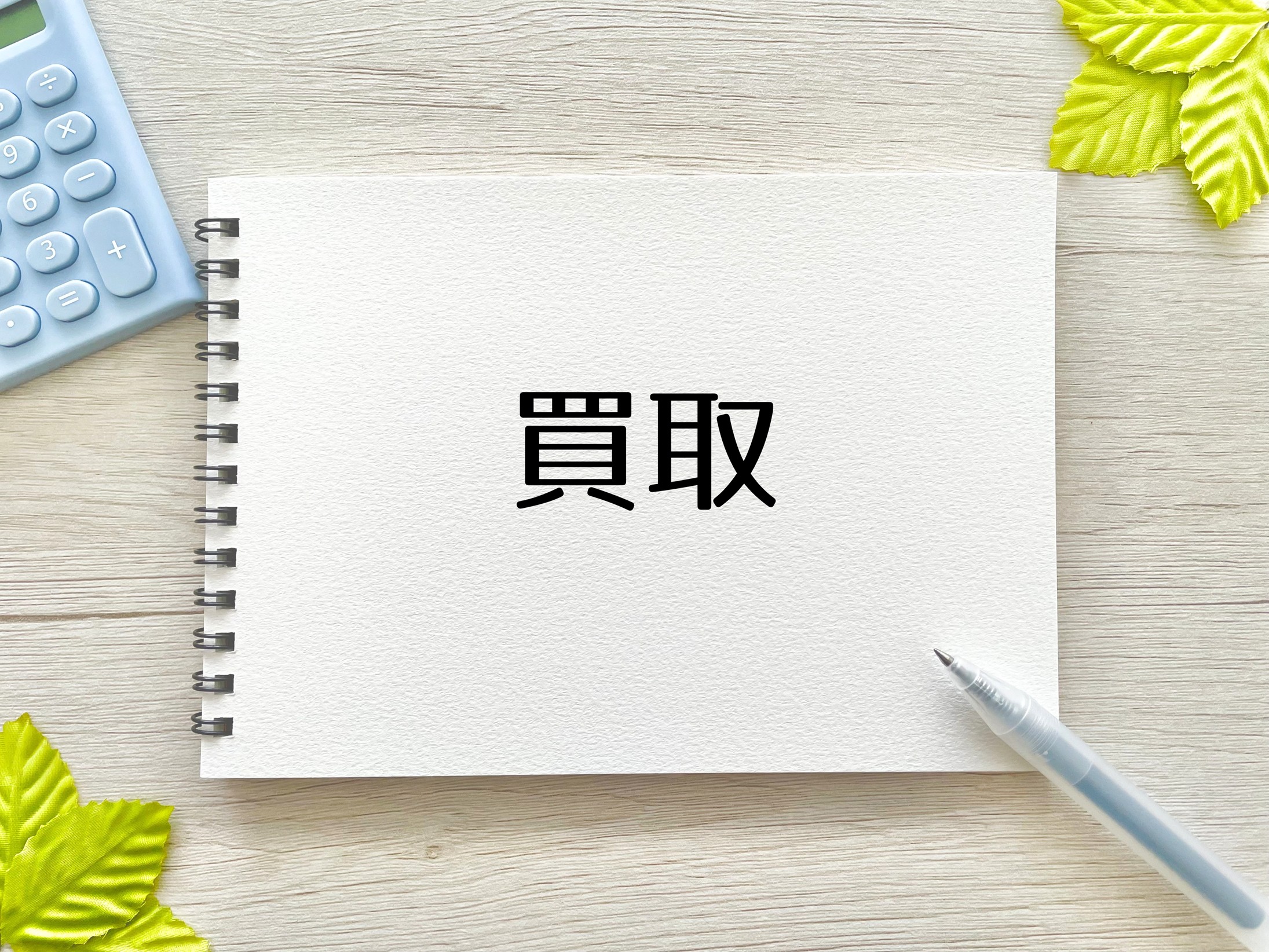共有持分は買取可能!メリットや相場・買取請求の方法を解説
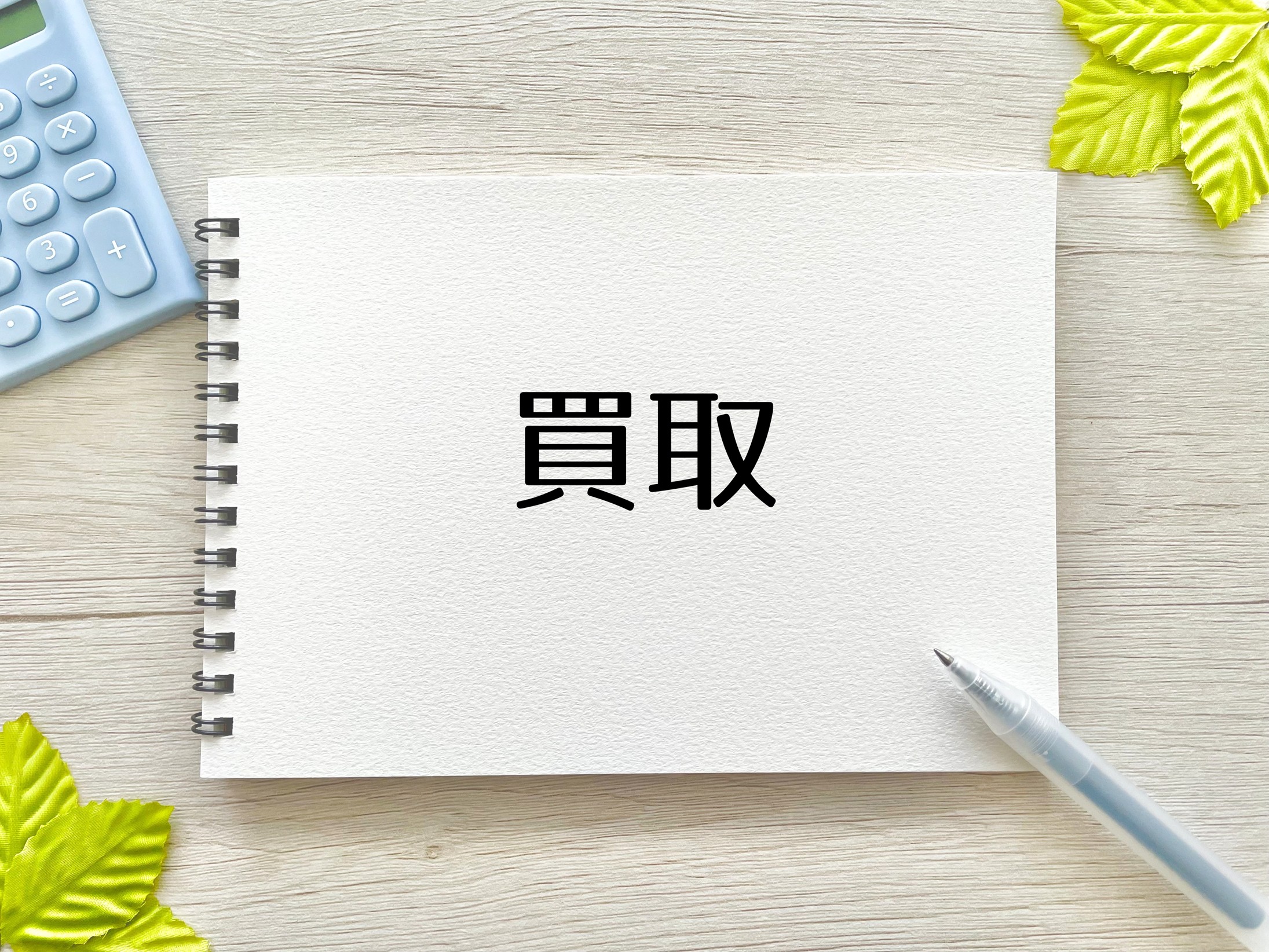
共有名義の不動産を所有している場合、複雑な共有状態を早期に解消したいと考える方も多いでしょう。
共有不動産を単独名義にする方法として、共有持分の買取があげられます。
当事者間で合意が得られれば、価格や条件は自由に設定可能です。
しかし、ほかの共有者が買取に応じてくれるとは限りません。
本記事では、共有持分を買取請求する方法や買取相場、共有状態を解消するその他の手段をまとめました。
自分の目的に合わせ、最適な処分方法を選択しましょう。
不動産の共有持分は買取できる?
共有名義の不動産を所有している場合、ほかの共有者から持分を買い取れます。
各共有者には、自己持分を単独の判断で処分する権利があるからです。
ほかの共有者から持分を買い取る場合、選択肢は以下の2パターンがあります。
| 買取の選択肢 | 効果・メリット |
|---|---|
| すべての持分を買い取る |
|
| 一部の持分を買い取る |
|
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、自分の共有持分を買取業者に売却するほうがスムーズです。
- 不動産を所有する必要がない
- 複雑な権利関係を解消できればよい
- ほかの共有者の持分を買い取る資金がない
不動産全体を取得したい場合のみ、ほかの共有者から持分の買取を検討しましょう。
参考:民法第252条|e-Gov法令検索
共有持分買取のメリット
共有持分における特有の制限・リスクを軽減するには、ほかの共有者から持分を買い取り、単独名義にするのが有効です。
ここでは、2つのメリットを見ていきましょう。
- 不動産を自由に管理・利用できる
- 不動産の資産価値が向上する
それぞれ解説します。
不動産を自由に管理・利用できる
共有名義の不動産は、共有者全員の合意がなければ変更を加えられません。
変更とは、以下のような行為を指します。
- 不動産全体の売却
- 大規模な増改築・用途変更
- 抵当権の設定
ほかの共有者からすべての持分を買い取ることで、上記の変更を単独の判断で行えるようになり、不動産の有効活用につながります。
さらに、不動産が単独名義になれば、将来的なリスクも軽減されます。
相続が発生すると権利関係が一層複雑になり、不動産に関する意思確認が難航するからです。
共有物に関する行為は、以下の分類で判断しましょう。
| 共有不動産に関する行為 | 共有持分の割合 |
|---|---|
| 保存 | 自己の持分のみで可能 |
| 管理 | 過半数の持分で可能 |
| 変更 | 不動産全体の取得、または共有者全員の合意で可能 |
参考: 民法第251条|e-Gov法令検索
参考:民法第252条|e-Gov法令検索
不動産の資産価値が向上する
一般的に、共有持分の売却相場は「共有不動産(全体)の評価額×持分割合×30%〜70%」とされています。
以下のようなリスクを加味して査定するため、市場価格よりも大きく割引されることが特徴です。
- 不動産の管理・利用に制限がある
- 共有者間のトラブルに巻き込まれるおそれがある
- 需要が低い(買い手が限られる)
ほかの共有者から持分を買い取り、不動産全体の権利を取得すれば、市場価格で売却できる可能性が高まります。
共有持分の買取請求は3パターン

共有持分を買い取りたい場合、ほかの共有者へ「買取請求」を行う必要があります。
買取請求の方法は、以下の3パターンです。
- ほかの共有者と交渉して買取する
- 「共有分分割請求」で買取する
- 「共有持分買取権の行使」で買取する
それぞれ解説します。
ほかの共有者と交渉して買取する
ほかの共有者に買取の意向を伝え、相手が同意してくれるかどうかを確かめます。
価格や条件などに法的な決まりはなく、当事者間の合意があれば成立可能です。
交渉によって買取を請求する際は、以下の流れで進めます。
- 買い取りたい理由を丁寧に説明する
- 価格や条件を提示する
- 相手が納得する落としどころを見つけるまで話し合う
- 合意が得られた内容で売買契約書を作成・締結する
- 所有権移転登記を行う
当事者間での話し合いが難航する場合は、不動産会社や弁護士に交渉を依頼しましょう。
「共有分分割請求」で買取する
相手が交渉による買取請求に応じない場合は、法的措置である「共有分分割請求」を行います。
共有分分割請求のおもな特徴は、以下のとおりです。
- 共有持分を持っているすべての人が請求できる
- ほかの共有者は請求を拒否できない
- 請求すると、不動産の分割方法を共有者全員で協議する義務が生じる
話し合いがまとまらない場合は、訴訟による判決で強制的に不動産の分割が行われます。
共有分分割請求訴訟における判決は、以下3つのいずれかです。
| 判決 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産そのものを分割し、共有者で分ける方法 |
| 代金分割 | ほかの共有者の共有持分を買い取り、単独名義にする方法 |
| 競売分割 | 不動産を競売にかけて売却し、代金を分割する方法 |
「代金分割」が認められれば、ほかの共有者の持分を買い取れますが、希望どおりの分割方法が選ばれるとは限りません。
「共有持分買取権の行使」で買取する
共有持分買取権は、不動産における義務を怠っている共有者から、強制的に持分を買い取る権利です。
成立条件が揃っていれば、共有物分割請求よりもスムーズに買取が実現します。
買取権の行使は、以下の条件を満たすと認められやすくなります。
- ほかの共有者が負担すべき維持費や税金を肩代わりしている
- 立て替えた維持費・税金が1年以上支払われていない
- 未払いに対して正当な理由がない
なお、居場所や連絡先の分からない共有者がいる場合は、裁判所に申し立てを行うことで、所在不明共有者の持分を取得可能です。
訴訟には多くの時間と費用がかかるため、最終手段として検討しましょう。
参考:民法第253条|e-Gov法令検索
参考:民法第262条の2|e-Gov法令検索
共有持分の買取相場を確認する方法

共有持分を買い取る際は、適正な買取価格を把握しておかなければなりません。
共有持分の価格は、以下の計算式で算出できます。
買取相場を知るために、まずは「不動産全体の価格」を以下の方法で確かめましょう。
- 不動産会社に査定を依頼する
- 公定価格を参考にする
- 不動産鑑定士に鑑定を依頼する
詳細を解説します。
不動産会社に査定を依頼する
不動産会社へ査定を依頼することで、手軽に不動産の相場を把握できます。
依頼できる査定は以下の2種類です。
| 種類 | 特徴 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 机上査定 | 不動産のデータのみで査定する |
|
| 訪問査定 | 実際の現場を見て査定する |
|
不動産の価格は、建物の修繕状況や土地の境界など、現地を見なければ把握できない要素で変動します。
そのため、訪問査定のほうがより実態に即した査定結果を得られます。
売却を決めている方は、机上査定を経ずに訪問査定を依頼しても問題ありません。
複数の業者に査定を依頼し、結果を比べることで、より正確な買取相場を把握できます。
公示価格を参考にする
国土交通省や都道府県が公表している「公示地価」や「基準地価」も、相場感の把握に役立ちます。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 種類 | 調査主体 | 調査地点 |
|---|---|---|
| 公示地価 | 国土交通省 | 標準値1㎡あたりの価格 |
| 基準地価 | 都道府県 | 基準値1㎡あたりの価格 |
公示価格は、実際に取引された価格(実勢価格)と異なるため注意しましょう。
公示価格から実勢価格を求める際は、以下の計算式を用いることが一般的です。
国土交通省の不動産情報ライブラリでは、売却予定の不動産と条件が似ている物件の実勢価格を閲覧できます。
ただし公示価格・実勢価格は、売却を予定している不動産の情報を加味した価格ではありません。
より正確な価格を知りたい場合は、不動産会社や不動産鑑定士への依頼を検討しましょう。
不動産鑑定士に鑑定を依頼する
不動産鑑定士は、不動産の適正な価値を評価する国家資格者です。
不動産鑑定士が作成する「鑑定評価書」は公的な証明能力があり、さまざまな場面で活用できます。
ただし、鑑定費用の相場は「20万円〜40万円程度」と高額なため、単に相場感を把握する目的で利用するのは不向きです。
不動産鑑定士に依頼するシーンは、おもに訴訟提起時になるでしょう。
共有物分割請求訴訟で価格合意が得られない場合、不動産鑑定士の鑑定によって価格を決めます。
当事者が選任した鑑定士では公平性に欠けるため、裁判所選任の鑑定士による鑑定結果が用いられます。
共有持分の買取相場に影響する要素
共有持分の価格は、不動産の査定によって算出されます。
査定時に見られるポイントや、価格に影響する要素は以下のとおりです。
- 不動産の立地
- 建物の状態
- 持分割合と共有者の数
- 共有持分の内訳
- 居住の有無
- ローン残債の有無
- 境界標の有無
それぞれ見ていきましょう。
不動産の立地
立地がよいほど「欲しい」と感じる人が多いため、不動産の評価が高まります。
好評価につながる具体的な条件は、以下のとおりです。
- 駅が近く、利用できる公共交通機関が多い
- 学校・病院・商業施設などへのアクセスがよく、利便性に優れている
- 公立小中学校の学区がよい(治安がよい)
- 線路・踏切・幹線道路などに面しておらず、周囲の騒音が少ない
好立地・好環境の物件は競争力があり、高額な査定がつく傾向にあります。
建物の状態
建物がある不動産の場合は、以下のような要素が査定額に影響します。
- 築年数
- 外装(劣化・破損・建物の傾きなど)
- 内装(水回りやフローリングなどの状況、シロアリ被害の有無など)
- 新耐震基準を満たしているか
こうした要素は物件ごとの個体差が大きく、現地を確認しないと高精度な査定ができません。
とくに戸建ては、屋根や外壁などの確認項目が多いため、正確な査定額を知るには「訪問査定」が必要です。
持分割合と共有者の数
共有不動産は、持分割合が大きいほど査定額が高くなる傾向にあります。
過半数を占める持分があれば不動産の管理行為ができ、実質的な支配力が高まるからです。
反対に、共有者の数が多いほど、不動産を活用できる幅は狭まります。
買主は、ほかの共有者との交渉・合意形成に費用と時間を費やさなければならないため、査定額は低くなりやすいでしょう。
共有持分の内訳
不動産は「建物のみ」「土地のみ」よりも、建物と土地をセットで売却するほうが高額査定につながります。
どちらか一方の権利のみでは、不動産の活用幅が狭まるからです。
- 相続した一戸建てを、自分は土地、弟は建物と名義を分けて所有している
- 不動産全体を売却したいが、弟から合意を得られない
上記の土地は、売却すると「底地」として扱われます。
底地とは、建物の持ち主に貸している状態の土地を指します。
底地は、自分の土地にもかかわらず自由に利用できないため、一般の買い手を見つけることは困難です。
買取業者への売却価格は、更地価格の10%〜15%程度と大きく値下がりする傾向にあります。
居住の有無
対象の不動産に共有者が居住している場合も、査定額は大幅に低くなります。
不動産を利用するためには、居住者に立ち退きを交渉しなければならず、買い手のリスクが大きいからです。
ただし、単身用マンションなどを賃貸物件として第三者が利用している場合は、収益性が高いと見なされて有利に働くこともあります。
査定額は、不動産会社の査定方法や得手・不得手、時期によっても変動することを考慮しましょう。
ローン残債の有無
ローンが残っている物件には抵当権が設定されているため、査定額が低くなります。
抵当権付きの物件を購入した買主は、さまざまなリスクを負うからです。
ローンが残っている不動産を買取業者に売る場合、業者は抵当権を解除するために複雑な手続きを踏まなければなりません。
こうした手間や法的リスクを加味して査定額を算出するため、市場価格よりも低い値がつきやすくなります。
夫婦の共有名義で不動産を購入しており、住宅ローンの残債があるケースでは注意が必要です。
境界標の有無
境界標は、土地の境界点を示すための標識であり、査定額算出の重要な要素になります。
境界標があれば、土地の所有範囲が明確になり、隣地とのトラブルを防止できるからです。
境界標がない不動産を売却する際は、土地家屋調査士などの有資格者に測量を依頼しなければなりません。
測量にかかる時間・費用を差し引くため、結果として査定額が下がる傾向にあります。
不動産が必要ない場合は「共有持分売却」も検討
ほかの共有者から持分を買い取り、自分の単独名義にすることで、複雑な権利関係を整理できます。
一方で「共有関係は解消したいが、不動産自体は必要ない」と考えている方もいるでしょう。
不動産を取得しなくてもよい場合は、自分の共有持分のみを売却するのも1つの方法です。
売却先の選択肢には、以下の3つがあります。
- 自分以外の共有者
- 第三者(仲介業者を経由)
- 共有持分専門の買取業者
もっともスムーズに売却できる可能性が高い相手は、自分以外の共有者です。
双方の合意があれば、価格や条件を自由に設定できます。
ただし、共有者との関係性が険悪な場合や、相手に資金力がない場合は、その他の売却先を検討しなければなりません。
現在の状況をふまえ、トラブルなく高値で売却できる方法を選択しましょう。
▼関連記事
内部リンク「共有持分 売却」
共有持分を高く売却するコツ

共有持分を第三者に売却する場合は、事前準備によって売却価格に大きな差が出ることも少なくありません。
売却を検討し始めたら、以下にもとづいて対策を講じましょう。
- 持分割合を増やす
- エリアに精通した不動産会社を選ぶ
- 共有持分を専門とする買取業者に依頼する
詳細を解説します。
持分割合を増やす
共有持分割合が大きくなるほど、不動産に対する支配力が高まるため、査定額が上がる傾向にあります。
たとえば、持分割合が過半数を占めると、不動産の管理に関する事項を決定できます。
管理行為を実行できれば、賃貸物件として収益を出せるため、不動産の評価が高まるのです。
資金に余裕がある場合は、売却前にほかの共有者から持分を買い取っておきましょう。
エリアに精通した不動産会社を選ぶ
エリアに根ざした不動産会社を選べば、高値で売却できる可能性が高まります。
地域密着型の業者は、商圏エリアの物件情報や市場動向を熟知しているからです。
エリアに精通した不動産会社の特徴は、以下のとおりです。
- 地元情報(人気の学区・商業施設、将来的な開発計画など)に詳しい
- 地域に根ざした独自の人脈がある
- 対応の柔軟性が高く、特殊な物件でも相談しやすい
結果として、不動産の価値を適正に評価してもらえる可能性が高くなります。
とくに、状態や条件がよくない共有持分の売却においては、該当地域に強みを持つ業者に依頼するのがおすすめです。
共有持分を専門とする買取業者に依頼する
共有持分の売却では、取り扱いに配慮すべき点が多数あります。
そのため、共有持分売却の実績がない不動産会社では、査定額が大幅に低くなったり、買取を断られたりするケースが少なくありません。
共有持分を専門とする買取業者を選べば、適正な査定額を算出するだけでなく、以下のようなサポートも受けられます。
- ほかの共有者との交渉・調整
- 法律事務所と連携したトラブル対応
- パートナー企業と提携したスピーディな審査・現金化
信頼できる業者を見極めることで、納得感の高い共有持分の売却が実現します。
共有持分の買取でよくある質問
ここでは、共有持分の買取に関して発生しがちな疑問を確認しましょう。
- 共有持分の買取相場はいくらですか?
- 共有持分を内緒で買取してもらうことはできますか?
- 共有持分を買取業者に売却した際に発生しがちなトラブルは何ですか?
- 共有持分の買取・売却にはどのような税金がかかりますか?
各質問に回答します。
共有持分の買取相場はいくらですか?
共有持分の売却額は、以下の式で目安を算出できます。
ただし、実際の買取相場は売却先によって変動します。
ほかの共有者に売却する場合は、上記の算出結果を参考に交渉可能です。
一方で、買取業者に売却する場合は、上記価格の3割〜5割程度になります。
共有持分は管理・活用が難しく、トラブルに巻き込まれるリスクもあるため、一般の買い手(個人)を見つけることは困難です。
第三者に売却したい場合は、買取業者への依頼が賢明です。
共有持分を内緒で買取してもらうことはできますか?
不動産全体の売却には「共有者全員」の同意が求められるものの、共有持分は単独の判断で売却できます。
内緒での売買を想定すると、相談先は「共有持分専門の買取業者」がもっとも適切です。
売却した事実は、いずれほかの共有者に知られることになるでしょう。
しかし買取業者に依頼すれば、トラブルが発生した際も迅速に対応してもらえます。
売却後の交渉は買取業者が引き受けるため、心理的な負担もかかりません。
共有者との関係性が悪い場合は、共有持分の買取実績が豊富な業者に相談しましょう。
共有持分を買取業者に売却した際に発生しがちなトラブルは何ですか?
悪質な買取業者に共有持分を売却すると、以下のようなアクションを起こす懸念があります。
- ほかの共有者に「あなたの持分も売ってください」と迫る
- 共有者が売却に応じないと、共有物分割請求訴訟を起こすことがある
ほかの共有者は、業者の担当者から唐突に営業され、不本意な状況に追い込まれます。
結果として当事者間の関係性が険悪になることが、もっとも発生しやすいトラブルの1つです。
共有持分を売却する際は、信頼できる業者を見極めることが重要です。
共有持分の買取・売却にはどのような税金がかかりますか?
納める税金は、共有持分の「購入時」と「売却時」で異なります。
| 項目 | 税金の種類 | 計算式・税率 |
|---|---|---|
| 購入時 | 不動産取得税 | 固定資産税評価額×3%(令和9年3月31日までの特例措置) |
| 売却時 | 譲渡所得税 |
|
参考: 国土交通省|不動産取得税に係る特例措置
参考:国税庁|土地や建物を売ったとき
譲渡所得税は、売却時に発生した利益(譲渡所得)にかかる税金で、共有持分の所有年数に応じて税率が変わります。
利益が出なければ確定申告は不要ですが、控除や特例を利用する場合は申告を検討しましょう。
まとめ:共有持分売却は専門買取業者への相談がおすすめ
不動産の共有状態を解消したい場合は、ほかの共有者の持分を買い取るか、自己持分の売却を検討しましょう。
不動産を取得する必要がない方には、共有持分買取業者への売却がおすすめです。
蔵正地所では、創業30年にわたり首都圏の共有持分買取を行ってきました。豊富な実績で培ったノウハウと、パートナー企業との連携をもとに、お客様にとって最適な提案をいたします。
「希望の条件で買い取ってほしい」「信頼できる業者に相談したい」とお考えの方は、蔵正地所へお問い合わせください。
関連記事:不動産売却の基礎知識まとめ|流れ・税金・必要書類・注意点を解説
関連記事:共有不動産を現金化する方法とは?高値で売却するコツや手順を解説
関連記事:共有持分は売却できる?トラブル防止策や相場・発生する税金を解説
この記事の監修者

小川 竜二 Ryuji Ogawa
蔵正地所株式会社/代表取締役
《資格》宅地建物取引士