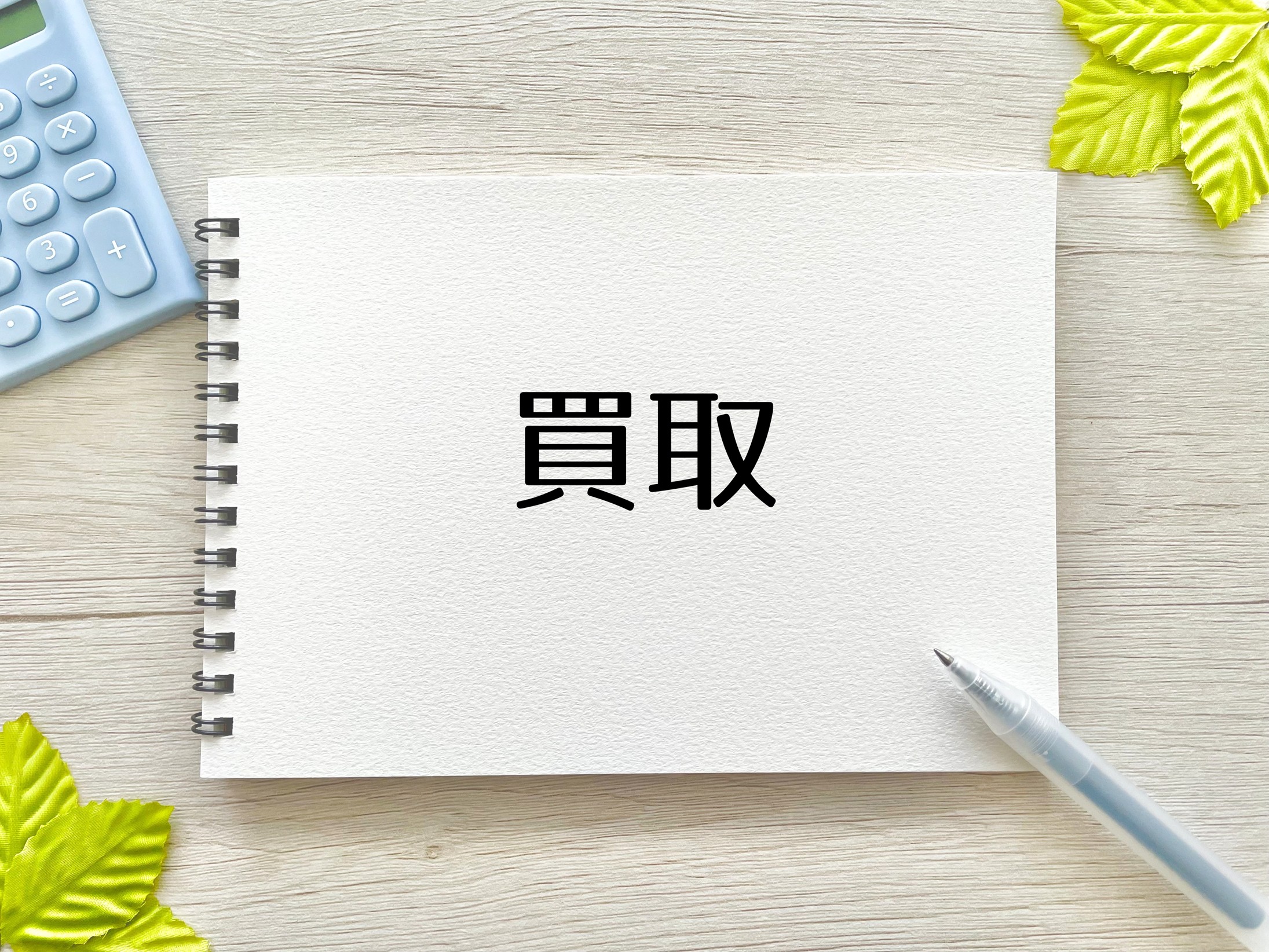共有不動産を現金化する方法とは?高値で売却するコツや手順を解説

権利関係が複雑で、自由に管理・処分できない「共有不動産」を、早期に手放したいと考える方は少なくありません。
共有不動産を現金化するうえで、不動産全体を売却する場合は「共有者全員の合意」が必要です。
共有者が売却に反対している場合や、話し合いの余地がない場合は、その他の選択肢を取る必要があります。
本記事では、共有不動産を現金化する5つの方法を、ケース別に解説します。
高値で売却するコツもまとめているため、共有不動産の処分にお悩みの方は参考にしてください。
共有不動産は全員の同意がなければ売却できない
複数人の共有名義になっている不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。
以下のような「共有物へ変更を加える行為」は、民法第251条によって制限されているからです。
- 不動産全体の売却
- 大規模な増改築・用途変更
- 抵当権の設定
ただし、共有不動産における自分の所有分(共有持分)は、ほかの共有者の同意を得ずに売却可能です。
以下のように、家族で共有名義の不動産を所有しているケースで考えてみます。
| 項目 | 共有持分割合 | 不動産売却への意見 |
|---|---|---|
| 母 | 2分の1 | 反対 |
| 兄弟 | 4分の1 | 反対 |
| 自分 | 4分の1 | 賛成 |
ほかの共有者が不動産の売却に反対していても、自分の持分(4分の1)は自由に処分可能です。
参考:民法第251条|e-Gov法令検索
共有不動産を現金化する5つの方法

共有不動産を売却する方法として、以下の5つがあげられます。
| 売却方法 | おすすめなケース |
|---|---|
| 共有者全員と合意して不動産全体を売却する |
|
| ほかの共有者に共有持分を売却する |
|
| ほかの共有者の持分をすべて買い取ったうえで売却する |
|
| 共有物分割請求訴訟を申し立てたうえで売却する |
|
| 第三者に共有持分のみを売却する |
|
各パターンの詳細を解説します。
1. 共有者全員と合意して不動産全体を売却する
ほかの共有者に売却の意向がある場合や、誰も不動産を利用していない場合に活用できる方法です。
通常は、売却益を持分割合に応じて共有者間で分配します。
不動産全体を売りに出すメリットは、市場価格に近い金額で売却できることです。
共有持分のみを売却する場合は、市場価格の3割〜5割程度になることが多く、共有者間で得られるトータルの売却益に大きな差が出ます。
一例として、市場価格が4,000万円の共有不動産を売却するケースで考えてみましょう。
「不動産全体を売却する場合」と「共有持分をそれぞれ売却する場合」では、得られる現金に以下の違いが生じます。
| 項目 | 共有持分割合 | 不動産全体を売却する場合 | 共有持分をそれぞれ 売却する場合 |
|---|---|---|---|
| 母 | 2分の1 | 2,000万円 | 不動産そのものを分割し、共有者で分ける方法 |
| 兄弟 | 4分の1 | 1,000万円 | 600万円〜1,000万円 |
| 自分 | 4分の1 | 1,000万円 | 300万円〜500万円 |
| 全員分 | − | 4,000万円 | 1,200万円〜2,000万円 |
ただし、反対者が1人でもいるとこの方法は実現できません。
2. ほかの共有者に共有持分を売却する
特定の共有者が不動産を利用しているケースでは、自分の共有持分をその共有者に買い取ってもらうことも1つの方法です。
不動産を利用している共有者に資金があれば、双方にとってメリットが大きい手段だといえます。
持分割合が増えることで、不動産の実質的な支配力が高まるからです。
たとえば、持分割合が過半数を占めると、不動産の管理に関する事項を決定できます。
不動産を賃貸物件として利用する、リフォームするなどの行為を単独の判断で行えるようになります。
ただし、共有者が複数人いる場合は「誰に買い取ってもらうのか」を慎重に見極めなければなりません。
不動産に対して行使できる権利にかかわるため、ほかの共有者とトラブルに発展するおそれがあります。
参考:民法第252条|e-Gov法令検索
3. ほかの共有者の持分をすべて買い取ったうえで売却する
ほかの共有者の持分を買い取り、自分の単独名義で売却すれば、通常の不動産と同様に市場価格で取引できます。
共有持分の売却相場が低いのは、不動産の利活用に制限があるからです。
実際に住んだり、賃貸で収益化したりできない不動産を欲しがる第三者(個人)はいません。
その点で、単独名義の不動産は需要があるため、共有持分よりも高値がつきやすくなります。
ただし、共有者全員の同意や、自身の資金力がなければ実現するのは難しいでしょう。
4. 共有物分割請求訴訟を申し立てたうえで売却する
共有者間での合意が得られない場合、共有物分割請求訴訟を申し立てることで、共有状態を解消できます。
共有を解消する方法は裁判で決まり、各共有者は判決に従わなければなりません。
時間・費用・精神面で負担が大きく、不本意な判決になるリスクもあるため、最終手段として検討するのがよいでしょう。
裁判では、共有不動産の分割方法として以下いずれかの判決が下されます。
- 分割方法1. 現物分割
- 分割方法2. 代金分割(賠償分割)
- 分割方法3. 競売分割(換価分割)
詳細を見ていきましょう。
分割方法1. 現物分割
共有不動産を物理的に分割し、それぞれ単独名義にする方法です。
公平性が高いことから、裁判においては現物分割が優先的に検討されるものの、実際に選択されることは多くありません。
建物は物理的に分割できないことに加え、土地の分筆によって一方の不動産価値が下がるおそれもあるからです。
たとえば、土地が使いにくい形状になったり、近接道路から離れてしまったりなどのケースが該当します。
分割方法2. 代金分割(賠償分割)
分割時の差額を金銭で補償する方法です。
代金分割には、以下2つの選択肢があります。
| 代金分割の選択肢 | 内容 | 認められやすい要件 |
|---|---|---|
| 全面的価格賠償 | 共有不動産を単独名義にし、対価として持分割合に応じた金銭をほかの共有者に支払う | 不動産の取得者に支払い能力があること |
| 一部価格賠償 | 現物分割によって不動産を分け、取得部分の価格差を金銭で補う | 現物分割によって不動産の価値が著しく損なわれないこと |
代金分割の採用は、不動産の状況や共有者の事情など、さまざまな要素を考慮して決定されます。
分割方法3. 競売分割(換価分割)
不動産を競売にかけ、売却代金を持分割合に応じて分ける方法です。
公平な分割方法ではあるものの、競売分割には以下のようなリスクが伴います。
- 市場価格よりも低い金額で売却されることがある
- 不動産を手放さなければならない場合がある
不動産に住んでいる、もしくは利用している共有者がいる場合、競売分割のデメリットはとくに大きくなります。
現物分割や代金分割が不可能なときには競売を命じられることがあるため、訴訟を起こすことは慎重に判断しましょう。
5. 第三者に共有持分のみを売却する
共有持分を、共有者以外の個人に購入してもらうのは難しいでしょう。
共有持分を買い取った買主は、以下のようなリスクを負うからです。
- 不動産に対する権利を行使できず、使い道がない
- 共有者間のトラブルに巻き込まれやすい
こうした理由から、共有持分は買取業者に売却するのが現実的だといえます。
共有持分専門の業者は、蓄積したノウハウや売却実績があり、一般的な不動産会社よりも高値で買い取ってくれる可能性があります。
トラブルへの対応体制が整っている業者も多いため、共有者間の関係性が悪化しているケースでも依頼しやすいでしょう。
共有不動産を高値で現金化するコツ

共有不動産は特有のリスクを伴うため、一般市場における売却では価格が低くなる傾向にあります。
高値を目指すには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 複数の業者に査定を依頼する
- 売却のタイミングを見計らう
- 共有持分買取に強みのある不動産会社を選ぶ
それぞれ見ていきましょう。
複数の業者に査定を依頼する
不動産会社を選ぶ際は、少なくとも2〜3社に査定を依頼しましょう。
査定額の基準や担当者の対応は、業者によって異なるからです。
多くの不動産会社において、査定は無料で対応しているため、複数社に依頼する金銭的なデメリットはありません。
注意点は「高額な査定額を提示する業者が必ずしもベストではない」ことです。
他社より高めの査定額を提示されても、それが買取価格になるとは限りません。
複数社の対応を比較し、信頼できる企業を見極めましょう。
売却のタイミングを見計らう
不動産の価格は、景気変動や需給バランスの影響を大きく受けます。
現金化を急いでいない場合は、市場動向を見極めたうえで売却活動を進めるほうが、高値で売れる可能性が高まるでしょう。
しかし、国内外における政治・経済状況の不確実性は高く、不動産市場は容易に分析できません。
そこで目安になるのが、控除・特例を適用できるタイミングです。
たとえば、相続した不動産を売却する場合は、以下の特例を利用できる可能性があります。
| 控除・特例の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 相続空き家を売却する際、譲渡所得から3,000万円を控除できる |
| 取得費加算の特例 | 譲渡所得税を計算する際、相続税額のうち一定金額を取得費として加算できる |
いずれも、適用要件を満たすには「相続してから3年以内」を目安に売却する必要があります。
譲渡所得税の節税につながれば、結果的に手残りが多くなるため検討してみましょう。
共有持分買取に強みのある不動産会社を選ぶ
共有持分専門の業者を選ぶメリットは、以下のとおりです。
- 独自のネットワークやノウハウがあるため、不動産の価値を高く評価してもらえる
- 不動産売却に必要な書類が不足していても買い取ってもらえる可能性がある
- 共有者間で生じたトラブルに対応してもらえる
共有持分の取り扱いに不慣れな業者を選ぶと、資産価値を適正に評価してもらえないおそれがあります。
共有不動産は通常の不動産と異なり、取引の際に配慮すべき要素が多数あるからです。
早期に、かつ高値で現金化したい場合は、信頼できる買取業者を選びましょう。
共有不動産を現金化する流れ
共有不動産のスムーズな売却を実現するために、現金化までの具体的なステップを把握しておきましょう。
- ほかの共有者と相談して現金化の方法を決める
- 売却先と売買契約を締結する
- 決済・所有権移転登記を行う
- 確定申告する
煩雑な手続きもありますが、買取業者へ依頼する場合はサポートを受けられます。
各ステップの詳細を見ていきましょう。
ほかの共有者と相談して現金化の方法を決める
ほかの共有者の持分を買い取る場合や、不動産全体を売却する場合は、話し合いのうえ合意を得る必要があります。
共有者が売却に前向きでないときは、共有持分のデメリットを伝えて交渉しましょう。
- 共有持分のみの売却では価格が大幅に下がる
- 共有者が高齢になると、税金や費用を支払えなくなる可能性がある
- 共有者の誰かが死亡した際、権利関係がさらに複雑になる
相続の発生によって共有者が増え、不動産の管理・処分が困難になることは、共有持分のとくに大きなリスクです。
建設的な議論をするためにも「なぜ共有状態を解消すべきなのか」を丁寧に説明しましょう。
売却先と売買契約を締結する
不動産全体、もしくは共有持分の売却が決まったら、売却先と売買契約を締結します。
売買契約書には以下のような事項が記載されているため、不明点がある場合は担当者に確認しておきましょう。
- 売買代金や手付金の金額
- 不動産の引渡し日
- 不動産の引渡し条件
- 税金の精算方法
- 契約不適合責任など
一般の買主に売却する場合、契約不適合責任には注意が必要です。
契約に適合した不動産を引き渡していないとき、買主に責任を追及されるリスクがあります。
なお、買取業者への売却では、契約不適合責任は免責されることが一般的です。
売却後のリスクを回避して不動産を現金化したい場合は、買取業者への売却を視野に入れましょう。
決済・所有権移転登記を行う
売買契約を締結したら、後日に決済・引渡し・所有権移転登記を行います。
当日の具体的な流れは、以下のとおりです。
| 所有権移転登記 | 所有権を買主へ変更する手続き |
| 税金精算 | 買主による負担分の受け取り |
| 関係書類・鍵の引渡し | 設備の説明書、測量図、合鍵を含めた物件の鍵など |
買取業者へ売却する場合は、上記の手続きを業者主導で行いますが、ほかの共有者へ売却する場合は自力で行わなければなりません。
契約書の作成や登記申請は専門知識が必要とされるため、司法書士に依頼することが一般的です。
手続きに費やす時間や、司法書士報酬などもふまえて売却先を検討しましょう。
確定申告する
共有不動産を売却し、利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告が必要になります。
申告期限は「売却翌年の2月16日〜3月15日」です。
譲渡所得が発生しているかどうかは、以下の計算式で算出できます。
計算結果がプラスになったら、原則的には確定申告が必要なため、早めに計算しておきましょう。
具体的な譲渡所得税の計算手順は、以下の記事で詳しく解説しています。
内部リンク「相続不動産 売却」
共有不動産の現金化でよくある質問

共有不動産の売却時に発生しやすい、以下の疑問に回答します。
- 共有不動産の売却相場はいくらですか?
- 共有不動産を現金化する際にはどのような費用がかかりますか?
- 共有不動産をトラブルなく売却する方法はありますか?
それぞれ見ていきましょう。
共有不動産の売却相場はいくらですか?
共有持分の売却額は、以下の計算式で算出できます。
ただし、上記は市場相場で売れた場合の金額です。
実際の売却相場は「誰に売るか」で大きく変動します。
ほかの共有者に売却する場合は、上記の算出結果を参考に交渉しつつ、双方が納得すればどのような価格でも取引可能です。
一方で、買取業者に売却する場合は、上記価格の3割〜5割程度になります。
共有持分は管理・活用が難しく、所有しているだけでリスクを伴うため、通常の不動産と比較して価格が下がります。
第三者の買主(個人)を自力で見つけることは困難なので、共有者間で売買できない場合は買取業者への依頼を検討しましょう。
共有不動産を現金化する際にはどのような費用がかかりますか?
不動産の売却時には、一般的に以下のような費用がかかります。
| かかる税金・費用 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却益(譲渡所得)にかかる所得税・住民税 |
| 印紙税 | 契約書や領収書の作成に必要な税金 |
| 登録免許税 | 登記申請にかかる税金 |
| 司法書士報酬 | 登記申請を司法書士に依頼した場合にかかる費用 |
| 仲介手数料 | 不動産を仲介で売却した場合にかかる費用 |
譲渡所得税は、売却で利益が出た場合のみ課税されます。
譲渡所得がある場合や、税金の控除・特例を利用する場合は、確定申告が必要です。
共有不動産をトラブルなく売却する方法はありますか?
まずは、ほかの共有者に共有持分のリスクを伝え、不動産全体を売却する方向で交渉しましょう。
しかし、共有者間の関係性が険悪な場合や、話し合いの余地がない場合は、自分の持分のみを売却するほかありません。
トラブルに発展する懸念があるなら、法律事務所と連携している専門業者に相談することをおすすめします。
なお、共有者に内緒で持分を売却しても、いずれは固定資産税の納税通知書などで事実を知られます。
トラブルを防ぐ意味でも、共有不動産の取り扱いに慣れた業者を選定することが賢明です。
まとめ:共有不動産の現金化は経験豊富な不動産会社へ相談しよう
共有不動産には、管理・処分の面で特有の制限があり、取り扱いが難しい傾向にあります。
「早期に現金化したい」「ほかの共有者と関係性がよくない」という場合は、共有持分の専門業者へ相談しましょう。
蔵正地所は、創業30年にわたり首都圏の共有持分買取を行っている不動産会社です。豊富な実績で培ったノウハウと、パートナー企業との連携をもとに、お客様の希望に最大限寄り添った提案をいたします。
トラブルには専門の法律事務所と連携し、責任を持って対応できる体制を整えています。
相続や離婚、その他の事情で悩みを抱えている方は、蔵正地所までお問い合わせください。
関連記事:共有持分は売却できる?トラブル防止策や相場・発生する税金を解説
関連記事:相続不動産を売却するには?流れや3,000万円控除・注意点を解説
関連記事:不動産売却の基礎知識まとめ|流れ・税金・必要書類・注意点を解説
この記事の監修者

小川 竜二 Ryuji Ogawa
蔵正地所株式会社/代表取締役
《資格》宅地建物取引士