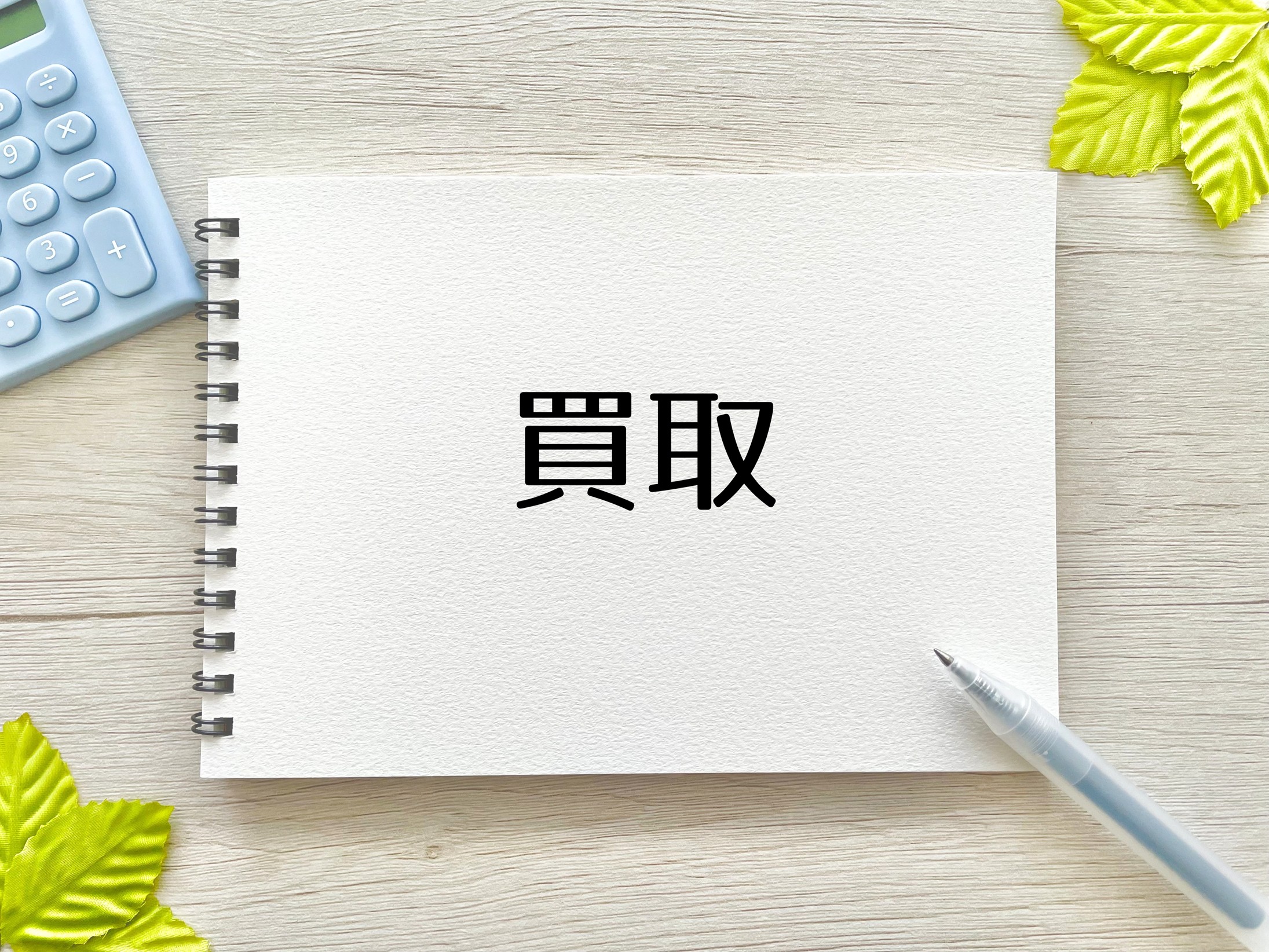電話でのお問い合わせは03-5695-2341
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18-20
相続不動産を売却するには?流れや3,000万円控除・注意点を解説

親や親族から不動産を相続したものの、利用予定がなく売却を考える方は少なくありません。
相続不動産を売却する際は、登記申請や査定など、多くの手続きが必要になります。
節税につながる特例も複数あるため、損をしないためには入念に準備を進めることが重要です。
本記事では、相続不動産を売却する流れや発生する費用、特別控除の適用条件などをまとめました。
手残りを最大限に増やしつつ、スムーズに売却したいとお考えの方は参考にしてください。
相続不動産を売却する流れ
相続不動産を売却する際は、最初に「遺言状の有無」を確認します。
遺言状がある場合、原則として遺言状の内容に沿って相続を進めます。
遺言状がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めなければなりません。
以下では、遺言状がないケースを想定して相続不動産の売却手順を見ていきましょう。
- 相続人を確認する
- 遺産分割協議を行う
- 相続登記(名義変更)手続きをする
- 不動産会社へ査定を依頼する
- 売買契約を締結する
- 決済し、不動産を引渡す
- 確定申告する
詳細を解説します。
1. 相続人を確認する
相続が発生したら、被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を集めて法定相続人(法律上相続の権利がある人)を洗い出します。
親族の相続順位は以下のとおりです。
| 相続順位 | 該当する人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 故人の子(死亡の場合は孫・ひ孫) |
| 第2順位 | 故人の父母・祖父母 |
| 第3順位 | 故人の兄弟姉妹(死亡の場合は甥・姪) |
法定相続人には、最低限保障された遺産の取り分(遺留分)があります。
遺言状や生前贈与で遺留分を侵害された場合、該当する相続人は侵害額を請求する権利があるため、相続人の確認は必ず行いましょう。
2. 遺産分割協議を行う
複数の相続人がいる場合、遺産分割協議で不動産の分け方を話し合う必要があります。
要点は以下のとおりです。
- 協議が終了するまで、相続不動産は全員の共有財産になる
- 協議は相続人の中の誰が進行してもよい
- 決まった内容は「遺産分割協議書」に記し、全員で署名捺印を行う
相続した不動産全体を処分するには、相続人(所有者)全員の同意が必要です。
売却を検討している場合は、遺産分割協議の時点で合意を得ておきましょう。
3. 相続登記(名義変更)手続きをする
相続不動産は、故人名義のままでは売却できないため、名義変更手続きである所有権移転登記(相続登記)が必要です。
相続登記の手続きは、以下の書類を用意したうえで法務局にて行います。
- 被相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
- 法定相続人の戸籍謄本(抄本)
- 法定相続人の印鑑証明書
- 法定相続人の固定資産課税明細書
- 新しく所有者になる人の住民票
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
手続きが煩雑であることから、相続登記は司法書士に依頼する方が多い傾向にあります。
売却先の不動産会社から紹介してもらえるため、事前に相談しておくとよいでしょう。
参考:法務局|相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
4. 不動産会社へ査定を依頼する
登記手続きを終えたら、不動産の価格を決める調査(査定)を依頼します。
査定方法は「机上査定」と「訪問査定」に分けられ、以下のような特徴があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 机上査定 |
|
| 訪問査定 |
|
実際に売却する際は、机上査定が済んでいても、改めて訪問査定が必要です。
5. 売買契約を締結する
査定結果が出たら、不動産の売買契約を結びます。
不動産会社が作成した「売買契約書」の読み合わせを行い、内容に納得できれば署名捺印します。
売買契約を締結する際に必要なものは、以下のとおりです。
- 本人確認書類
- 実印
- 印鑑証明書
- 印紙代
- 不動産会社へ支払う仲介手数料(仲介の場合)
- 不動産登記済証など
売買契約の締結時は、不動産の売却代金の一部を「手付金」として受け取ります。
手付金の相場は、売買代金の5%〜10%程度です。
契約書の内容に不明点がある場合は、契約を結ぶまえに担当者へ質問しておきましょう。
6. 決済し、不動産を引渡す
決済日は、不動産の引渡しと同時に手付金以外の残金を受け取ります。
売買契約書で特別に定めていない限り、決済と引渡しは同日に行われることが一般的です。
当日は、以下のような手続きを行います。
| 所有権移転登記 | 所有権を買主へ変更する手続き |
| 税金精算 | 買主による負担分の受け取り |
| 関係書類・鍵の引渡し | 設備の説明書、測量図、合鍵を含めた物件の鍵など |
受け取った売却代金は、遺産分割協議書の決定事項にもとづいて各相続人で分配します。
7. 確定申告する
相続不動産の売却によって利益が出た場合は、確定申告が必要です。
分配された所得を、各相続人が「売却の翌年」に申告しなければなりません。
譲渡所得(利益)が出ているにもかかわらず申告しない場合は、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税(悪質な場合)
損失が生じた場合は、原則として確定申告の必要はありません。
参考:国税庁|確定申告を忘れたとき
参考:国税庁|延滞税について
相続不動産の売却にかかる税金・費用

相続で取得した財産に限らず、不動産を売却する際は、一般的に以下の費用がかかります。
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税
- その他諸経費
具体的な金額や計算方法を見ていきましょう。
譲渡所得税
不動産の売却において利益が出た場合は、売却益(譲渡所得)に所得税や住民税が課されます。
譲渡所得の計算式と税率は以下のとおりです。
| 項目 | 不動産の所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 |
|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 |
|
具体例で計算方法を見ていきましょう。
参考:国税庁|土地や建物を売ったとき
課税対象となる金額(譲渡所得)を計算する
課税対象となる金額を計算する際は、以下の費用を把握しておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 売買契約書に記載されている価格 |
| 取得費 | 不動産の取得時にかかった費用から、減価償却費を引いた金額 |
| 譲渡費用 | 相続不動産を売却する際にかかった費用 |
一例として、以下の条件をもとに譲渡所得を計算してみましょう。
- 売却価格:3,000万円
- 取得費:1,500万円
- 譲渡費用:80万円
計算結果がプラスになる(譲渡所得がある)場合は、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得に税率を当てはめる
譲渡所得がある場合は、不動産の所有期間に応じた税率で納税額を計算します。
上記と同様、譲渡所得が1,420万円だった場合の計算例を見てみましょう。
| 長期所有(5年超)で売却 | 1,420万円(譲渡所得)×20.315%=288万4,730円 |
| 短期所有(5年以下)で売却 | 1,420万円(譲渡所得)×39.63%=562万7,460円 |
所有年数は「被相続人の所有期間」を引き継ぐため、長期所有の税率(20.315%)が適用されるケースが多くなります。
印紙税
契約書や領収書の作成で課税される「印紙税」は、売却価格に応じて税額が変わります。
| 売却価格 | 課税額 |
|---|---|
| 100万円超〜200万円以下 | 200円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 500円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
郵便局などで「収入印紙」を購入し、契約書へ貼り付けることで納税が完了します。
参考:国税庁|不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
登録免許税
不動産の相続や売却における「登記申請」を行う際にかかる税金です。
相続不動産を売却する際は、以下のタイミングで登記申請が必要になります。
- 故人から相続人へ名義を変更するとき
- 相続人(所有者)から買い手に名義を変更するとき
各登記申請における登録免許税の税額は、以下のとおりです。
| 登記申請の種類 | 登録免許税額 |
|---|---|
| 相続による所有権移転 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 売却による所有権移転 |
|
売却時にかかる登録免許税は、譲渡所得を計算する際の「譲渡費用」に含められます。
参考:国税庁|登録免許税の税額表
その他諸経費
相続不動産の売却においては、税金以外に以下の費用がかかることもあります。
| 種類 | 発生するケース | 費用感 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介を依頼して売却した場合 | 売却金額の3%+6万円+消費税(売却価格が400万円超の場合) |
| 司法書士報酬 | 登記申請を司法書士に依頼した場合 | 5万円〜10万円 |
さらに、土地の測量を実施する場合は「測量費」、建物を取り壊す場合は「建物解体費」などが発生します。
参考:国土交通省|不動産取引に関するお知らせ
相続不動産を3年以内に売却した際に適用できる特例

相続不動産を売却した際、要件を満たせば税金控除の特例を適用できる可能性があります。
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
- 相続空き家を売却した際の3,000万円特別控除
- 居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円特別控除
いずれの特例も、相続開始から「3年以内」の売却を目安にしているため注意しましょう。
詳細を解説します。
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
譲渡所得税を計算する際に、相続税額のうち一定金額を「取得費」として加算できる特例です。
不動産にかかる税金は高額になることが多いため、要件を満たせば相続人の税負担を軽減できるでしょう。
取得費加算特例は、相続税と譲渡所得税のダブルパンチによる負担を軽減するものです。
そのため、株式の譲渡による事業所得・雑所得には適用されません。
参考:国税庁|相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
適用の要件
以下の要件をすべて満たす場合、取得費加算特例を利用できます。
- 相続や遺贈によって財産を取得している
- 財産の取得者に相続税が課税されている
- 財産を相続税の申告期限から3年を経過する日までに売却している
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。
そのため「相続開始から3年10ヶ月以内」に売却しなければ、本特例を利用できません。
取得費加算特例の適用可否は、国税庁のチェックシートで判断することをおすすめします。
取得費加算特例の税金シミュレーション
取得費加算特例を利用した場合の納税額を計算してみましょう。
シミュレーションは、以下の条件をもとに行います。
| 相続した財産の内容 |
|
| 納めた相続税額 |
|
| 売却した不動産の状況 |
|
まずは、取得費に加算できる金額がいくらなのかを計算します。
次に、課税される金額(譲渡所得)を求めます。
最後に、長期譲渡所得に対する税率で税額を計算します。
取得費加算特例を適用しない場合、同様の条件では「751万6,550円」の税金を納める必要があります。
税負担を大幅に軽減できるため、要件を満たす場合は利用を検討しましょう。
相続空き家を売却した際の3,000万円特別控除
相続不動産が被相続人の居住用財産(空き家)だった場合、売却時に譲渡所得から3,000万円が控除される特例です。
共有名義で相続すると、各共有者に控除が適用されます。
たとえば、兄弟2人が共有名義で不動産を相続した場合、合計6,000万円が控除されます。
ただし、各相続人が控除の適用を受けるには、土地と建物の両方を共有名義にしなければなりません。
適用の要件
空き家特例は控除額が大きいため、控除の条件も厳しくなっています。
おもな要件は以下のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
- 相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかった
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用として利用していない
- 一定の耐震基準を満たしている
- 「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けていない
- 親子や夫婦など、特別の関係がある人に売ったものでない、など
令和6年1月1日以降の譲渡においては、耐震基準の条件が緩和されています。
買主が、譲渡翌年の2月15日までに耐震リフォームまたは取り壊しを行う場合、現状のまま譲渡しても控除を適用可能です。
参考:国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
空き家特例の税金シミュレーション
空き家特例の適用時は、譲渡所得を以下の計算式で算出します。
以下の条件下において、空き家特定の適用「あり」と「なし」の譲渡所得税を比較してみましょう。
| 不動産の条件 |
|
| 各項目の金額 |
|
- 特例適用なし:(3,000万円−150万円−600万円)×20.315%=457万875円
- 特例適用あり:(3,000万円−150万円−600万円−3,000万円)×20.315%=0円
条件を満たす場合は、迷わず利用すべきです。
居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円特別控除
自宅として利用している不動産を相続した場合、売却時に譲渡所得から3,000万円が控除される特例です。
被相続人と同居していた場合などに利用できます。
適用要件や税金の計算方法を見ていきましょう。
適用の要件
マイホーム特例は、以下の要件を満たすことで適用できます。
- 現に自分が住んでいる家である
- 以前住んでいた家の場合は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていない
- 親子や夫婦など、特別の関係がある人に売ったものでない、など
適用可否は、国税庁のチェックシートで判断するのがおすすめです。
参考:国税庁|マイホームを売ったときの特例
マイホーム特例の税金シミュレーション
譲渡所得は空き家特例と同様に、以下の計算式で算出できます。
以下の条件下で、マイホーム特例の適用による節税効果をシミュレーションしてみましょう。
- 父(被相続人)と暮らしていたマイホームを相続
- 所有期間:3年(短期譲渡所得)
- 取得費:4,000万円
- 売却価格:5,000万円
- 売却時の諸費用:200万円
- 特例なし:譲渡所得税=(5,000万円−4,000万円−200万円)×39.63%=317万400円
- 特例あり:譲渡所得税=(5,000万円−4,000万円−200万円−3,000万円)×39.63%=0円
控除額が大きいため、節税効果も高いことが分かります。
マイホーム特例は空き家特例と異なり、相続開始の前後を問わずに利用可能です。
相続不動産を売却する際の注意点
相続不動産を売却する際は、経済的なメリットが最大化するように売却活動を進めましょう。
具体的な注意点は、以下のとおりです。
- 共有名義の不動産売却は全員の同意を得ておく
- 税金は相続人全員で負担する
- 取得費の証明になる書類を探しておく
- スムーズな売却を目指す
それぞれ解説します。
共有名義の不動産売却は全員の同意を得ておく
共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ以下の変更行為を実行できません。
- 不動産全体の売却
- 大規模な増改築・用途変更
- 抵当権の設定
売却を前提として話を進める場合は、遺産分割協議の段階で相続人の同意を得ておくとよいでしょう。
なお、共有名義になっている不動産を、自分の所有権割合(共有持分)のみ売却する際は、ほかの共有者の同意が必要ありません。
売却の合意が得られなかった際の手段として、内容を押さえておきましょう。
▼関連記事
内部リンク「共有持分 売却」
参考:民法第251条|e-Gov法令検索
税金は相続人全員で負担する
相続不動産の売却時にかかる税金・諸費用は、相続人全員で負担しなければなりません。
たとえば、不動産売却時の諸費用を代表者1人が立て替えたら、のちにほかの相続人と精算する必要があります。
共有不動産の場合も、各共有者が持分割合に応じて固定資産税・維持費を負担します。
参考:民法第253条|e-Gov法令検索
取得費の証明になる書類を探しておく
取得費とは、相続不動産の「購入時」にかかった金額のことを指します。
取得費を証明するには、購入当時の以下のような書類が必要です。
- 売買契約書
- 領収書
- 登記簿謄本
- 固定資産税の納税通知書など
取得費を証明できる書類が見つからない場合は、不動産の売却価格の5%を取得費とみなして譲渡所得を計算しなければなりません。
取得費の証明をできると課税譲渡所得がどのように変わるのか、一例をあげてシミュレーションしてみましょう。
- 父(被相続人)が1人で暮らしていた実家を相続
- 取得費:1,000万円
- 売却価格:2,000万円
- 譲渡費用:100万円
- 証明なし:課税譲渡所得=2,000万円−(2,000万円×5%)−100万円=1,800万円
- 証明あり:課税譲渡所得=2,000万円−1,000万円−100万円=900万円
実際の取得費は、売却価格の5%よりも高いケースが多いでしょう。
そのため、取得費不明によって5%ルールが適用されると、本来の課税譲渡所得よりも高額になり、納税額が増えてしまいます。
安易に5%ルールを適用せず、取得費の証明手段を探して税負担を軽減しましょう。
参考:国税庁|取得費が分からないとき
スムーズな売却を目指す
「取得費加算特例」や「空き家特例」は、3年以内を目安に売却することで適用可能です。
相続が発生したら、売却に向けて早めに準備することをおすすめします。
不動産の売却にかかる平均期間は、中古マンションで85.3日、中古戸建てで97.3日とされています。
条件のよくない物件は、さらに多くの日数がかかることも珍しくありません。
売却を急ぐ場合は、仲介よりも時間のかかにりくい「買取」を選択しましょう。
参考:公益財団法人東日本不動産流通機構|首都圏不動産流通市場の動向(2024年)
相続不動産の売却でよくある質問

相続不動産の売却において、多くの方が以下のような疑問を抱いています。
- 相続した土地を5年以内に売却するメリットは何ですか?
- 相続した不動産を焦って売ってはいけないのはなぜですか?
- 相続不動産の売却で確定申告が不要なケースはありますか?
回答を見ていきましょう。
相続した土地を5年以内に売却するメリットは何ですか?
不動産の所有期間が5年を超えると、長期譲渡所得として税率が下がります。
税率は「不動産を売却する年の1月1日時点での所有期間」で、以下のように判断されるからです。
| 項目 | 不動産の所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 |
|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 |
|
所有期間は「被相続人の購入日」を引き継ぎます。
被相続人が5年を超えて所有していた不動産の場合、相続してすぐに売却しても長期譲渡所得の税率が適用されます。
参考:国税庁|土地や建物を売ったとき
相続した不動産を焦って売ってはいけないのはなぜですか?
相続では「遺産を換金して分ける」「相続税の支払いに充てる」など、売り急ぐ理由が多数あるでしょう。
しかし、焦って売ると以下のような事態を招き、手残りが少なくなりかねません。
- 適用できる特例を見逃す、または用意すべき書類が間に合わない
- 売却期限がシビアになり、価格交渉で不利になる
さらに、売却を急ぐと相続人との協議が不充分になり、後々トラブルに発展するおそれもあります。
こうしたリスクを回避するためには、十分な期間を設けて準備を進めることが重要です。
相続不動産の売却で確定申告が不要なケースはありますか?
相続不動産の売却後に確定申告が不要なのは、利益が出なかった(譲渡所得がマイナスになった)場合です。
以下の計算式で算出した数値がゼロ以下であれば、確定申告の必要はありません。
譲渡所得があった場合でも、以下の要件を満たす「給与所得者」は確定申告が不要です。
- 給与所得以外の所得の合計が20万円以下
- 給与をもらっている勤務先は1か所である
- 勤務先で年末調整を受けた
個人事業主の場合は、譲渡所得が20万円以下であっても、ほかの所得との合計額が20万円を超えると確定申告が必要になります。
なお、不動産売却における特例を適用する際は、確定申告が必須になるため注意しましょう。
まとめ:相続不動産は早めに売却活動を行おう
相続不動産の売却においては、譲渡所得税の節税につながる特例が複数あります。
特例を適用するための売却期限は「3年以内」が目安になるため、早めに各相続人と合意形成し、不動産会社の選定を進めましょう。
相続不動産を共有分割にした場合、共有持分の処分に困るケースがあります。
「ほかの共有者の同意を得られていないが、自分の持分のみ売却したい」と考えている方は、蔵正地所にご相談ください。
共有持分の専門業者として長年培ったノウハウと、豊富な買取実績をもとに、あなたのご希望に寄り添った提案をいたします。
法律事務所との連携で、トラブル対応への体制も整えているため、相続不動産の問題を抱えている方は蔵正地所にお問い合わせください。
関連記事:不動産売却の基礎知識まとめ|流れ・税金・必要書類・注意点を解説
関連記事:共有不動産を現金化する方法とは?高値で売却するコツや手順を解説
関連記事:共有持分は売却できる?トラブル防止策や相場・発生する税金を解説
この記事の監修者

小川 竜二 Ryuji Ogawa
蔵正地所株式会社/代表取締役
《資格》宅地建物取引士